更新日:2024年11月14日
家計はどれくらい節約すればいい?賢い節約方法をお金のプロが解説
家計を節約したいと思ってはいても、何をどう減らせばいいのか悩んでいる人は多いのではないでしょうか?ポイントは支出割合の確認と、使い過ぎの項目の見極めです。理想の支出割合を考え方や、具体的な節約の方法をご紹介します。

- この記事の要点
-
- 何にどれくらいお金を使うか、自分にとって理想の支出割合を考える
- 現在の支出割合をもとに節約する項目を決める
- 節約の基本として固定費と変動費の使い方も見直す
- 固定費の見直しは慎重さも必要、プロに相談するのもよい
-
この記事の監修者

-
ファイナンシャルプランナー(CFP®資格/1級FP技能士)、生活経済ジャーナリスト
坂本 綾子
大手出版社の女性誌・経済紙等でフリーランスの記者として金融・経済記事を執筆。2010年にファイナンシャルプランナー事務所を設立。中立的な立場で金融商品やサービスを開設する記事の執筆に加えて、自治体の消費生活センター等でお金のセミナー講師も行う。消費者の家計相談にも対応している。
-
大手出版社の女性誌・経済紙等でフリーランスの記者として金融・経済記事を執筆。2010年にファイナンシャルプランナー事務所を設立。中立的な立場で金融商品やサービスを開設する記事の執筆に加えて、自治体の消費生活センター等でお金のセミナー講師も行う。消費者の家計相談にも対応している。
理想の支出割合は?
何にどれくらいお金を使うかは、どのようなライフステージにいるかで違ってきます。
独身で一人暮らしの時期、結婚して夫婦2人の時期、子どもが生まれたけれどまだ幼い時期、子どもの教育費がかかる時期など。どのようなライフステージでも必要な支出を確保しながら貯蓄もするには、支出割合や貯蓄率を意識するのがポイントです。
下の表は、ライフステージ別の支出割合の目安を作成したものです。地域により家賃や物価には差がありますし、同じライフステージにいる世帯であってもお金の使い方は違ってくるでしょう。
支出の割合に絶対的な正解は存在しません。ただし、バランスの取れない食事が健康に悪影響を与えるように、支出のバランスが悪いと生活に不都合が生じたり、貯金が難しくなる可能性があります。
支出割合の目安をもとに、理想の支出割合と、理想に近づくための節約のポイントを紹介します。
支出割合の目安
一人暮らし単身者の場合
| 項目 | 目安割合 | 手取り収入 30万円の場合 |
|---|---|---|
| 貯蓄 | 15% | 45,000円 |
| 食料 | 14% | 42,000円 |
| 住居 | 25% | 75,000円 |
| 光熱・水道 | 5% | 15,000円 |
| 家具・家事用品 | 2% | 6,000円 |
| 被服および履物 | 5% | 15,000円 |
| 保健医療 | 2% | 6,000円 |
| 交通・通信 | 8% | 24,000円 |
| 教養・娯楽 | 10% | 30,000円 |
| その他 | 14% | 42,000円 |
- その他の消費支出は、理・美容費、交際費、趣味の費用、おこづかいや使途不明金など
1人暮らしの場合、年齢や収入にもよりますが、住居費の割合が最も高くなるケースが多くあります。特に家賃や住宅価格が高い都心では、支出の50%近くを住居費が占めている人もいらっしゃいます。
しかし、できれば25%まで、多くても30%以内に抑えることを目標にしましょう。食費が多いのも1人暮らしの特徴です。つい外食が増えてしまうのが原因です。
健康にもかかわるので、やみくもに節約する必要はありませんが、20%までを目安に。残りの費目の使い方にも気を付けて、手取り収入の15%程度は貯蓄に回したいところです。
夫婦2人暮らしの場合
| 項目 | 目安割合 | 手取り収入 45万円の場合 |
|---|---|---|
| 貯蓄 | 25% | 112,500円 |
| 食料 | 18% | 81,000円 |
| 住居 | 22% | 99,000円 |
| 光熱・水道 | 4% | 18,000円 |
| 家具・家事用品 | 3% | 13,500円 |
| 被服および履物 | 4% | 18,000円 |
| 保健医療 | 2% | 9,000円 |
| 交通・通信 | 8% | 36,000円 |
| 教養・娯楽 | 6% | 27,000円 |
| その他 | 8% | 36,000円 |
- その他の消費支出は、理・美容費、交際費、趣味の費用、おこづかいや使途不明金など
夫婦2人暮らしの場合、共働きの世帯は子どもの養育費や教育費の心配がないため、経済的に余裕が生まれます。いずれ子どもを持つ予定の夫婦にとっては、この時期は貯め時にあたります。可能なら世帯の手取り収入の3割を目標に貯めましょう。
世帯収入が多くなるので、その分食費の割合が相対的に下がります。住居費は20%程度、多くても30%以内に抑えて、レジャーなど残りの費目にもお金を回して生活を楽しむことも大事にしたいですね。
メリハリのあるお金の使い方を心掛けましょう。
夫婦と子供(小学生以下)の場合
| 項目 | 目安割合 | 手取り収入 50万円の場合 |
|---|---|---|
| 貯蓄 | 20% | 100,000円 |
| 食料 | 20% | 100,000円 |
| 住居 | 21% | 105,000円 |
| 光熱・水道 | 5% | 25,000円 |
| 家具・家事用品 | 3% | 15,000円 |
| 被服および履物 | 4% | 20,000円 |
| 保健医療 | 3% | 15,000円 |
| 交通・通信 | 8% | 40,000円 |
| 教育 | 4% | 20,000円 |
| 教養・娯楽 | 4% | 20,000円 |
| その他 | 8% | 40,000円 |
- その他の消費支出は、理・美容費、交際費、趣味の費用、おこづかいや使途不明金など
子どもが生まれると、養育費、教育費がかかってきます。ただし、小学生以下なら食事の量もまだ少なく、3歳から5歳の子どもは「幼児教育・保育の無償化」により親の所得に関わりなく授業料や保育料が無償です。
また、高校卒業までの子どもには児童手当が支給されます。2024年10月の児童手当拡充により多くの家庭が恩恵を受けられます。そのため、この時期も貯蓄を増やす良い機会であると言えます。
将来の子どもの教育資金や住宅購入の頭金、老後資金などを見据えて、手取りの20%以上を目標に貯蓄しましょう。住居費を30%以内に抑えるのは、シングルか家族か、子どもがいるかいないか、子どもの年齢に関わらず共通の節約ポイントです。
夫婦と子供(中学生以上)の場合
| 項目 | 目安割合 | 手取り収入 50万円の場合 |
|---|---|---|
| 貯蓄 | 20% | 50,000円 |
| 食料 | 20% | 110,000円 |
| 住居 | 21% | 115,000円 |
| 光熱・水道 | 5% | 20,000円 |
| 家具・家事用品 | 3% | 20,000円 |
| 被服および履物 | 4% | 20,000円 |
| 保健医療 | 3% | 15,000円 |
| 交通・通信 | 8% | 40,000円 |
| 教育 | 4% | 40,000円 |
| 教養・娯楽 | 4% | 30,000円 |
| その他 | 8% | 40,000円 |
- その他の消費支出は、理・美容費、交際費、趣味の費用、おこづかいや使途不明金など
子どもの成長に伴い生活費が増えていきます。食費をはじめ、中学生以上になると子どもに携帯電話を持たせる家庭も多く、部活動や塾の費用など子どもの希望や個性に合わせた教育費の支出も増加します。住宅を購入して住宅ローンを抱える家庭もあるでしょう。
進路にもよりますが、専門学校や大学まで進学する予定なら、その時期に向けて教育資金の準備が必要です。
一方で、老後を意識する年齢に近づいてきます。支出が増える年代ではありますが、これまで以上に支出のバランスを意識し、手取りの10%は貯蓄に回しましょう。共働きなら10%以上の貯蓄を目標にしましょう。
自分の支出割合をもとに節約する費目を決める
現状の支出割合を確認する
家計の節約にはまず支出割合を確認してまずは現状を把握する必要があります。家計簿を付けていない人は、給与振込銀行の通帳やWEB明細、クレジットカードの明細、スマホ決済の履歴、現金払いならレシートをもとにざっくりでかまわないので確認しましょう。
キャッシュレス払いがメインであれば、家計簿アプリに連動させるとさまざまな支払いを自動的に集計して簡単に収支を把握できるので便利です。
目標とする支出割合を決める
現在の支出割合が把握できたら、貯蓄にどれくらい回すかを含めて目標とする支出割合を決めます。貯蓄は、毎月一定額を積み立てる先取り貯蓄がおすすめです。収入から先に貯蓄分を取り分け、残りで生活することで自動的にお金が貯まっていきます。
先取り貯蓄について詳しく知りたい方は「お金を貯めるには「貯まる仕組み」を作ること!」の記事を参考にしてください。
現状の収支の中で減らすべき費目があるなら、いくら削減するのかと、その方法を考えます。張り切って無理な計画を立てると、途中でお金が足りなくなり、積み立てた貯蓄を取り崩してしまうことになります。頑張ればできそうな目標を設定するのがコツです。
また、何のために節約するのか、節約により削減した支出で何を手に入れるのか、目標を明確にすると節約のモチベーションが上がるためおすすめです。
節約生活の基本、固定費、変動費をそれぞれ見直す
では、具体的な節約方法を紹介しましょう。支出には毎月ほぼ一定額を支払う固定費と、使い方により金額が流動的な変動費があります。まずは固定費の削減方法です。
固定費の削減方法
固定費は、一度見直せば、効果が続くメリットあるので、該当する項目があるならぜひ実行しましょう。特に三大固定費と呼ばれる「保険」「住宅ローン」「通信費」は見直すと効果が大きくなります。
生命保険を見直す
死亡保障や医療保障などを確保するために入る生命保険ですが、結婚した、子どもが生まれた、住宅ローンを組んで住宅を購入した、子どもが自立したなどライフステージが変化したときが見直し時です。
保障が足りなければ万一の際に困ってしまいますし、逆に多すぎると保険料を払いすぎることになります。適切な保障内容となっているか見直すことで保険料の負担が下がるケースがあります。
持ち家の人は住宅ローンを借り換えて金利を見直す
金利が低い住宅ローンに借り換えることで、毎月の返済額を減らすことができます。支払う利息の総額が減る可能性もあります。
ただし、借り換えには手数料などの費用がかかるので、その費用を払ってもメリットがあるかを確認しましょう。そのためには、借り換えのシミュレーションを事前に行ってみることです。ファイナンシャルプランナーに相談するか、シミュレーションに対応する金融機関もあるようです。
また、金利が低い変動金利の住宅ローンは、半年ごとに金利が変動し、将来的には金利が上がる可能性もあります。
金利が上がれば返済額も増加します。変動金利への借り換えは、金利が上昇した際には繰り上げ返済を行って金利負担を減らせるだけの貯蓄を手元に持っていることが条件です。
賃貸の人は更新のタイミングで家賃交渉や収入に合った住居費へ転居
家賃の負担が大きいなら、更新のタイミングで家賃を下げてもらえないか交渉してみましょう。
交渉が難しい場合は収入に見合った住居への転居も検討しましょう。公的な住宅は更新料がかからないところが多く、民間の賃貸相場よりも家賃が安いケースもあります。民間の賃貸も、最近は敷金や礼金が不要であったり少なく済むところもあります。
所得が一定額以下、子どもがいるなどの条件を満たせば家賃補助がある自治体もありますので確認してみましょう。
通信費を見直す
インターネット・スマートフォンの普及により、この10年ほどの間に家計支出の中で大きく増えているのが通信費です。
支出割合としては高くなくても、もっと安くできないか見直してみましょう。まずは選択しているプランが自分の使い方に合っているか確認からはじめます。
キャリアを変更して格安SIMに乗り換えればもっと安くなるケースもあります。仮に月3000円安くなれば、夫婦と子ども1人の3人家族なら世帯では1万円弱の節約、年間では10万円以上の差になります。
ガス・電気の料金プランの見直す
電気は自由化により選択肢が増えました。ガスと電気を同じ会社にすることで割引が受けられるケースもあります。
ネット比較サイトなどでもっと安くならないかシミュレーションしてみましょう。
サブスク、ジム代、習い事代を見直す
サブスクリプションやジム代など毎月費用がかかるものは、クレジットカード払いや銀行口座引き落としなどが一般的です。銀行の預金通帳やクレジットカード明細をこまめに確認しないと、ほとんど使っていないのに忘れたまま料金だけ払い続けているケースがあります。
改めて見直し、不要なものや利用する頻度が低いものは解約を検討しましょう。
変動費の削減方法
変動費はお金を使うたびに意識しなければならないので少し面倒ですが、できるものから取り組んでみましょう。
1回あたりの節約額は少なくても積み重なるとそれなりの金額になります。変動費の節約術には次のようなものがあります。
自炊をする、コンビニの利用を控える
外食の回数を減らし、なるべく自炊をするだけでも食費を削減できます。仕事帰りにコンビニでお菓子や飲料を買う習慣があるなら、週に一度スーパーで安くまとめ買いすることで削減できるでしょう。
ふるさと納税を活用し、食費を抑える
ふるさと納税は実質2,000円で返礼品を受け取ることができます。2,000円以上の食品をもらえるなら差額分がお得になります。
2,000円を除く全額を控除できる「寄付額の上限」を守ることと、必ず申告をして税金の還付を受けることが必須です。
趣味娯楽費を抑える
福利厚生の一環で、ホテルやレジャー施設の優待が受けられる会社もあるので、勤務先の状況を確認しましょう。
手持ちのクレジットカードなどの優待内容も確認して利用できるものは活用しましょう。
交際費を抑える
自分のルールを決めて予算内で納めましょう。月当たりの飲み会や食事会の回数を決める、1回あたりの費用の上限を決めておく、2次会以降は参加しないなどです。
三大固定費の見直しは効果が高いが慎重さも必要
家計を節約したいなら、お金の使い道別の支出割合を確認してみましょう。比率が高い項目があるなら、もっと減らせないかを考えます。無理なく貯蓄に回せる比率で先取り貯蓄も始めましょう。
保険、住宅ローン、通信費は三大固定費と呼ばれています。見直しによる節約効果は高いですが、知識や事前にシミュレーションする慎重さも必要です。ファイナンシャルプランナーへ相談し、自分に合った固定費削減方法についてアドバイスをもらうことも検討してはいかがでしょうか。
専門家にお金のお悩みを相談したい
保険以外にも家計の見直しや資産形成の方法など、お金に関するさまざまな相談ができます。
お気軽にご利用ください。
ファイナンシャルプランナー無料相談
専門資格を持つファイナンシャルプランナー(FP)にオンラインで相談ができます。
ライフプラン表を用いた、プロの視点での課題分析から、家計の見直しやNISAやiDeCoを使った資産形成の方法などの提案を受けることができます。
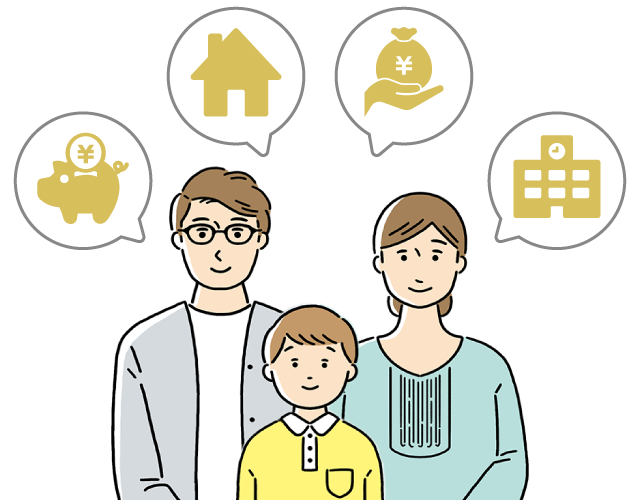
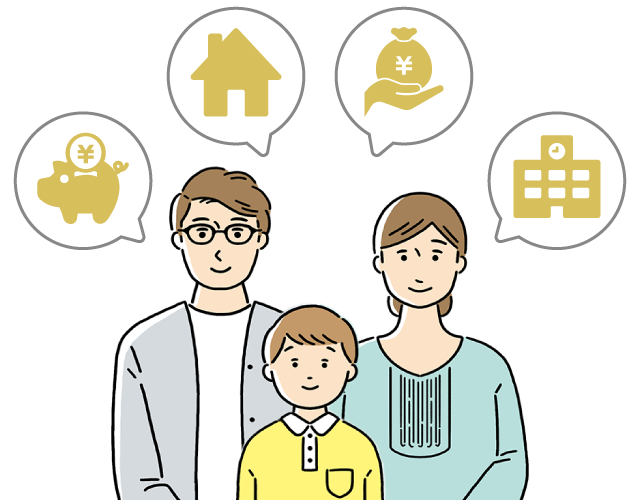
この記事の関連コンテンツ
-
理想の支出割合は?
-
自分の支出割合をもとに節約する費目を決める
-
節約生活の基本、固定費、変動費をそれぞれ見直す
-
三大固定費の見直しは効果が高いが慎重さも必要