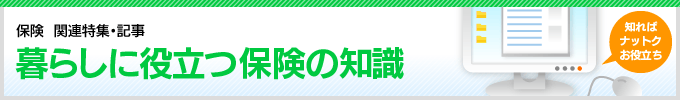個人年金保険の仕組みとメリット
個人年金保険は、60歳や65歳など予め決めた年齢から、一生涯または一定期間、毎年年金が受け取れる保険です。預貯金や一般的な投資商品などに比べて目的が明確になり資金作りが行いやすいこと、また、定期的にお金が受け取れるので、資産を取り崩していく不安感がないことが魅力です。
個人年金保険には、5年とか10年といった一定期間だけ年金を受け取れるタイプのほか、一生涯にわたって年金が受け取れる終身タイプもあります。終身年金は、早く亡くなった人の資金を長生きした人の年金原資に充てる、まさに保険ならではの相互扶助システム。保険料が高いのがネックですが、どんなに長生きしても資金が底をつく可能性がない安心感は、他の商品には代えられないものでしょう。
年収600万円で年8500円の節税効果
一定の条件を満たした個人年金保険には、一般の生命保険料控除とは別に、支払った保険料の一定額が毎年の所得から控除され、その結果、所得税や住民税の負担が軽減されるメリットがあります(表1)。たとえば、年収600万円の会社員の場合、所得税・住民税あわせて最大8500円(表2)の節税に。一般的な個人年金は、加入時の予定利率が期間中ずっと適用されることから、低金利下での加入は利回り的には魅力が薄れますが、税効果を考慮すれば預貯金より有利と言えるでしょう(市場金利に連動して利率が見直されるタイプもあります)。
表1:生命保険料控除の金額
| 年間支払保険料合計(注) | 控除額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 〜25,000円 | 支払金額 |
| 25,001〜50,000円 | 支払金額×1/2 + 12,500円 | |
| 50,001〜10,000円 | 支払金額×1/4 +25,000円 | |
| 100,001円〜 | 50,000円 | |
| 住民税 | 〜15,000円 | 支払金額 |
| 15,001〜40,000円 | 支払金額×1/2 + 7,500円 | |
| 40,001〜70,000円 | 支払金額×1/4 +17,500円 | |
| 700,001円〜 | 35,000円 |
- ※その年に支払った金額から、剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額。
表2:年収600万円の場合の税効果
| 個人年金保険に加入した場合 | 個人年金保険に加入しない場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | |
| 納付税額 | 121,200円 | 238,100円 | 126,200円 | 241,600円 |
| 納付税額 合計 | 359,300円 | 367,800円 | ||
- ※保険料払込期間65歳年金保険(保険料1万円/月)に加入した場合(夫:40歳以上会社員、妻:専業主婦、子ども:15歳以下1名。2010年の税制で試算)
- 個人年金保険への加入の有無で年間8,500円の差が出ます。
- 単純計算*をすると、保険料払込期間25年間で納税額に212,500円(8,500円×25年)の差が出ます。
- *現在の年齢、税制、家族構成等を基に計算しています。子どもの成長や税制等によって25年間の合計額は異なります。
ただし、控除を受けられるのは定額型の個人年金保険のうち、以下の条件を満たした契約となるので、注意が必要です。
・年金受取人=契約者または契約者の配偶者
・保険料払込期間が10年以上
・年金支払開始日は被保険者が60歳以上で、10年以上の定期年金または終身年金
国が案じているからこそ
ところで、個人年金保険に対し、このような税制優遇があるのは何故でしょう。それはとりもなおさず、国が公的年金だけでは安心な老後を送るのが難しいと認め、自助努力を促したいという意図に他なりません。新しい年を迎えるにあたって、将来の備えについて考えてみてはいかがでしょう。ただし、個人年金は途中で解約した場合の返戻金が、払い込んだ保険料を大きく下回ることがあるので、無理なく続けられる保険料の範囲で設計することをお忘れなく。