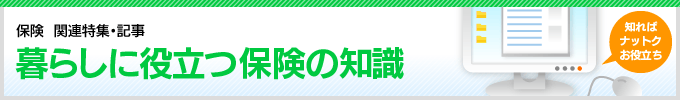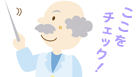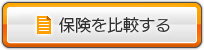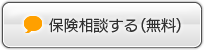1.�����ی����T���͂ǂ̂��炢����H
�͂��߂ɐ��x�̊T�v���m�F���܂��傤�B�����ی��͂��̓��e�ɉ����āu��ʁv�u�l�N���v�u���v�ɕ��ނ���A�N�Ԃ̎x���z�ɉ����Ă��ꂼ��̋敪���Ƃɍő�4���~�i���v12���~�j(��1)�̏����T�����F�߂��Ă��܂��B
�T���������z�͏����ŁA�Z���łňقȂ�A�ڂ����͉��L�̎Z���ŋ��߂����z�ƂȂ�܂��B
�y�}�\1�z
| �x���ی����i1/1~12/31�j | �T���z�i�����Łj |
|---|---|
| 20,000�~�ȉ� | �x���ی����S�z |
| 20,000�~��~40,000�~�ȉ� | �x���ی����~1/2+10,000�~ |
| 40,000�~��~80,000�~�ȉ� | �x���ی����~1/4+20,000�~ |
| 80,000�~�� | 40,000�~ |
�y�}�\2�z
| �x���ی����i1/1~12/31�j | �T���z�i�Z���Łj |
|---|---|
| 12,000�~�ȉ� | �x���ی����S�z |
| 12,000�~��~32,000�~�ȉ� | �x���ی����~1/2+6,000�~ |
| 32,000�~��~56,000�~�ȉ� | �x���ی����~1/4+14,000�~ |
| 56,000�~�� | 28,000�~ |
- �i���j�x���ی����́A���ߋ��Ȃǂ�����ꍇ�͂��̋��z�������������c��̋��z�ƂȂ�܂��B
2�D�T�����邽�߂ɕK�v�ȏ����́H
�����ی����T���͔N�������������͊m��\���Ŏ邱�Ƃ��ł��܂��B�ʏ�ł���A���N10������11�����A�_�Ă���ی���Ђ���ی����T���ؖ����������Ă���̂ŁA�N�������ɊԂɍ����܂��B
�������A�_��12���ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�́A���̏���N�������ɔ��f���邱�Ƃ͓���̂ŁA�m��\���ōT�������Ă��炤���ƂɂȂ�܂��B
�ʏ�̏����ł̊m��\���̊�����3/15�ł�����A�N�����ɍT���ؖ��������Ă���ł��\���Ԃɍ����܂����A�ҕt�\���ł����炻�̗��N��1/1����5�N�ȓ��ł���A�ŋ��̊ҕt�����܂��̂ŁA����Ɏ��Ԃ̐S�z�͗v��܂���B
3�D�ی����̕�������_��̎d���ōT���z���ς��H
�ی����̕������Ƃ��āu�������v�u���N�����v�u�N�����v�u�ꎞ�����v������A�܂Ƃ߂ĕ����قǕی����͊����ɂȂ�܂��B
�������A12���Ɍ_��ƂȂ����ꍇ�͕K�������u�ی����������������v�Ƃ͂����Ȃ��ł��B�ł́A�ȗ��������`�ňȉ��̂悤�ȃP�[�X���l���Ă݂܂��傤�B
�ی�����������1���~�A�N����12���~�̕ی���12���Ɍ_���ꍇ�A������1��������1���~�����T���ΏۂɂȂ�܂���B�������N�����ɂ���A�x���ی�����12���~�ƂȂ�8���~�̍T�������܂��B���̍��������Ŋz�ɒ����ƁA�ŗ���10���̐l�ł����7000�~�̐ߐł��\�ł��B
���̂��Ƃ���A���̃^�C�~���O�ł̔N�����_��́A��������芄���ȕی����Ƃ������ƈȊO�ɂ�����Ƀ����b�g�̂���_����@�ɂȂ邱�Ƃ�������܂��B
�ł́A�N�������ی����̈����ꎞ�����ł͂ǂ��ł��傤���B�ی����T���Ɋւ��Ă͔N���������N����̂ɑ��A�ꎞ�����͕ی����̎x����������_�N�x�݂̂̍T���ƂȂ�A���N����͎��܂���B
�܂��A������_����Ԓ��ɖS���Ȃ��Ă��܂����ꍇ�A�ꎞ�����ł͊��ɕ������ی����͕Ԋ҂���Ȃ��Ƃ������X�N������܂��̂ŁA
�ی����̊����ł�قǂ̍����Ȃ�����́u�N�����v�̕����I�����₷���ł��傤�B
12���_��Ƃ����^�C�~���O�ł́A�_�N�x�͊m��\���̕K�v���o�Ă��܂��ς킵����������܂���B������2�N�ڂ���́A�ی���Ђɂ����܂����x���ی����̌����z��N�������ɊԂɍ����悤�ɑ����Ă����ꍇ������A��������ȍT���ؖ������͂����i�K�ŁA�Ζ���ō��ւ��Ă����A
�N�������ōT�����s�����Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�܂��A�����2�N�ڂ���ł����ی����̎x�������@���������ɂ��邱�Ƃɂ���Ă��N�������ł̍T�����\�ɂȂ�܂��B�ی��������������̕��́A�܂��ő���̍T������̂ɊԂɍ����܂��̂ŁA�N���̕ی����̕������Ŋҕt�Ŋz�̎�肱�ڂ��������悤�����T��������悤�ɂ��܂��傤�B
�i��1�jH23�N12��31���ȑO�Ɍ_�������鋌�_��Ɋ�Â��T���z�́A��L��3�敪�ł͂Ȃ��u��ʁv�u�N���v��2�敪�ƂȂ�A�����ł̍T���z�͍ő�Ŋe50,000�~�A�Z���łł�35,000�~�ƂȂ�܂��B
�i��2�j2026�i�ߘa8�j�N���́A�q��Ďx���̈�Ƃ��āA23 �Ζ����̕}�{�e�������鐢�т̈�ʐ����ی����T�����ő�60,000�~�Ɉ����グ���܂��B
�o�T�F�ߘa7�N�x �Ő������̊T�v�i�����J���ȊW�j�i�����J���ȁj