更新日:2023年10月4日
ペット保険に関するトラブルはなぜ起こる? ペット保険でトラブルにならないために
ペット保険に関するトラブルはなぜ起こる? 飼っている犬・猫の病気やケガに備えるペット保険でトラブルにならないために、ペット保険の特性をしっかり理解しましょう。また、ペット保険に加入するときに気を付けたいポイントもまとめました。

- この記事の要点
-
- ペット保険のトラブルは、商品の補償対象や内容を十分に理解していなかったために発生することが多い
- ペット保険は、病気やケガにあたらない場合は補償されない
- 商品によって補償内容が異なるので、加入前にしっかりと確認することが大切
-
この記事の監修者

-
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
田辺 南香
ライフプランから見た家計管理・保険・住宅などマネーに関するアドバイスや、セミナー・Webサイト・雑誌等で情報発信を行う。主な書著「“未来家計簿”で簡単チェック! 40代から間に合うマネープラン」(日本経済新聞出版社)、「隠すだけ!貯金術」「家計簿いらずの年間100万円!貯金術」「女ひとり人生 お金&暮らしの不安が消える本」(KADOKAWA メディアファクトリー)。
-
ライフプランから見た家計管理・保険・住宅などマネーに関するアドバイスや、セミナー・Webサイト・雑誌等で情報発信を行う。主な書著「“未来家計簿”で簡単チェック! 40代から間に合うマネープラン」(日本経済新聞出版社)、「隠すだけ!貯金術」「家計簿いらずの年間100万円!貯金術」「女ひとり人生 お金&暮らしの不安が消える本」(KADOKAWA メディアファクトリー)。
ペット保険に関するトラブルとは?
ペット保険とは
ペット保険は、主に犬や猫のペットが動物病院で診療を受けたときの治療費を補償する保険です。
「通院補償」「入院補償」「手術補償」の3つの補償があり、一般的には、1年ごとの更新をして一生涯の補償を継続することが可能です。ただし、更新時の健康状態などによっては、まれに更新できないケースもあります。また、保険料は年齢とともに上がる可能性があります。契約前にペット年齢が上がったときの保険料も確認しておくとよいでしょう。
また、ワクチン接種や健康診断などの予防的な措置、去勢や避妊手術、健康維持のためのサプリメントやビタミン剤などはペット保険でカバーされません。そのほかに、補償の対象外となる病気やケガがあり、商品によって違いがあります。
さらに、補償割合が50%や70%などの商品やプランがあったり、免責金額(保険金が支払われない金額)や待機期間(加入から補償開始されるまでの待ち期間)などがあったりして、治療費全額は補償されないケースがよくあります。
補償割合は低いほど、免責金額は高いほど、待機期間は長いほど保険料が安くなりますので、保険料負担を考慮のうえ、商品やタイプを選ぶことが大切です。
ペット保険に関するトラブルとは?
商品によって補償する範囲やその内容が異なるため、ペット保険ではさまざまなトラブルが発生しがちです。
具体的な例を見てみましょう。
- ① 保険金支払限度額50万円の保険に加入中、治療費全体で20万円支払った。保険金を20万円もらえると思っていたが、10万円しか受け取れなかった。
- ② 補償割合50%のプランにもかかわらず、支払った治療費の半分以下しか保険金を受け取れなかった。
- ③ 治療費を1万円支払ったが、保険金を受け取れなかった。
- ④ 治療が長引き2週間入院。しかし10日分しか補償されなかった。
- ⑤ 保険に加入して40日目にがんと診断。その後治療したが、保険金を受け取れなかった。
- ⑥ ヘルニアで入院・通院したが、保険金を受け取れなかった。
- ⑦ 病歴のない10歳のペットが加入できなかった。
- ⑧ 契約が無効になった。
ペット保険に関するトラブルにはこのような例があります
ペット保険のトラブルケース
上記のようなトラブルは、商品の補償対象や内容を十分に理解していなかったために発生することが多いです。それぞれ考えられるトラブルの原因や補償内容を確認しておきましょう。
<A>全額補償ではないタイプの例
ケース①:保険金支払限度額50万円の保険に加入中、治療費全体で20万円支払った。
保険金を20万円もらえると思っていたが、10万円しか受け取れなかった。
加入していたプランが補償割合50%の保険だった例です。もしくは、免責金額が10万円だったり、1回あたりの手術や入院に限度額が設定されていたりという原因も考えられます。
ケース②:補償割合50%のプランにもかかわらず、支払った治療費の半分以下しか保険金を受け取れなかった。
免責金額が設定されていた可能があります。
支払った治療費が20万円、補償割合50%、免責金額2万円の場合では、
(治療費20万円−免責金額2万円)×補償割合50%=9万円(保険金)となります。
ケース③:治療費を1万円支払ったが、保険金を受け取れなかった。
免責金額を設定していた可能性があります。仮に免責金額が2万円なら、2万円以下の治療費を支払った場合には全額自己負担になります。
ケース④:治療が長引き2週間入院。しかし10日分しか補償されなかった。
手術を含む連続した入院の補償限度を10日とする商品が、このケースに該当します。そのほか、年間の入院限度日数が20日や30日など設定されている商品もあります。たとえば、入院20日限度の商品に加入していて、すでに10日間の入院で10日分支払われていたなら、同じ年にさらに14日間入院しても支払われるのは10日分となります。
そのほか、全額補償ではないケースとして、通院や入院、手術の年間回数に限度がある場合や、1回あたりの上限額が設定されている商品もあります。
<B>待機期間がある例
ケース⑤:保険に加入して40日目にがんと診断。
その後治療したが、保険金を受け取れなかった。
「待機期間をがんは60日、そのほかの病気は30日、ケガはなし」など、がんとそのほかの病気、ケガで異なる待機期間が設定されている商品だったことが考えられます。待機期間中に該当する病気を発症した場合は、補償開始後も補償されません。
<C>補償対象外の病気の例
ケース⑥:ヘルニアで入院・通院したが、保険金を受け取れなかった。
免責事由のひとつとして、特定の病気を補償の対象外とする商品があります。どの病気を対象外にするかなどは商品によって異なり、椎間板ヘルニアや膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)、通称パテラなど比較的ペットがかかりやすい病気でも補償されないケースがあります。
<D>加入年齢の制限を過ぎていた例
ケース⑦:病歴のない10歳のペットが加入できなかった。
新規で加入できる年齢を8歳までや12歳までなど、制限を設けているのが一般的です。10歳前後で加入を検討する場合は、加入可能年齢をしっかりチェックする必要があります。
なお、新規加入可能年齢を過ぎても、原則ペットが生きているかぎり終身まで更新ができるのが一般的です。しかし、更新時の健康状態などを理由に更新できないケースや、治療中の病気に関して補償の対象外となったり、保険料が割り増しになったりする場合もあります。
<E>告知をしっかりしていなかった例
ケース⑧:契約が無効になった。
人の医療保険などと同様に、契約時にはペットが過去にかかった病気や、現在治療中または経過観察中の病気、6か月以内の診察や検査、治療などについてきちんと告知する必要があります。
病歴などによって加入できない場合もありますが、違反して告知せずに加入できたとしても、保険金が支払われなかったり、契約が解除されたりすることもあります(告知義務違反)。
ペット保険でトラブルにならないために
多くのトラブルの原因は商品内容、補償内容の認識不足です。商品によって補償内容が異なりますので、加入前にしっかりと補償内容を確認することが大切です。重要事項説明書で、細かい点まで把握することをおすすめします。
小型犬は膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)を発症しやすいなど、ペットによってかかりやすい病気を調べ、検討中のペット保険では補償されるのか否かを、事前にチェックしておきましょう。
ペット保険では、補償開始前に発症していた既往症や先天性の病気、予防可能な感染症(フィラリア症や狂犬病など)、予防的な措置(健康診断や検査、ワクチン、マイクロチップの挿入など)、臍(さい)ヘルニア・鼠径(そけい)ヘルニア、帝王切開や去勢・避妊手術など、病気やケガにあたらない場合は補償されないのが一般的です。
主なチェック項目は以下のとおりです。
- 加入可能年齢
- 補償対象(通院・入院・手術)
- 補償割合
- 支払限度(回数・日数・金額)
- 免責金額
- 待機期間(ケガ・病気・がん別)
- 免責事由(補償対象外の病気やケース)
- 更新時条件(年齢、そのほか)
- 保険料、割引の有無
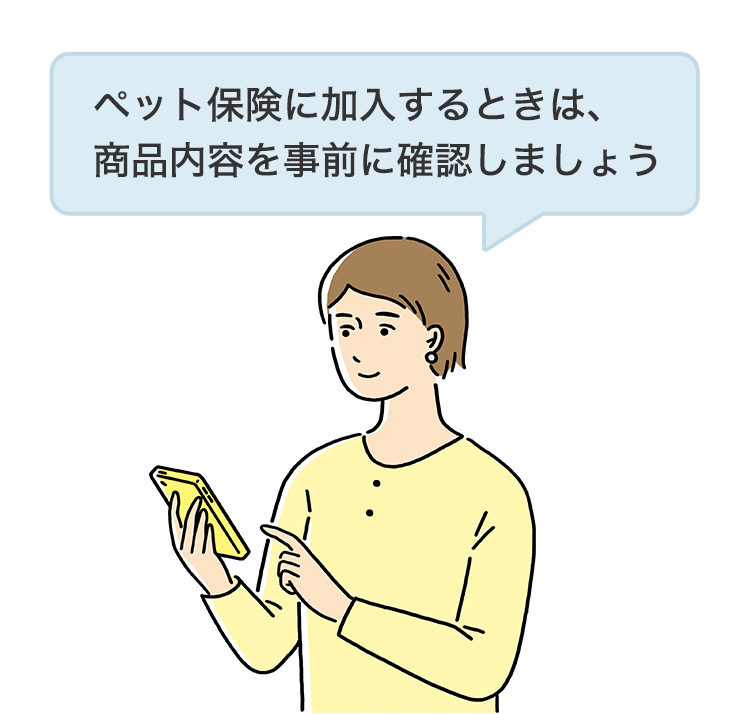
まとめ
事前の商品内容の確認で、多くのトラブルを防げますので、しっかりチェックしましょう。さらに、せっかく加入しても、告知義務違反で保険金を受け取れなかったり、契約解除になったりしないよう、契約時にもれなく告知しましょう。
また、多くのペット保険は1年更新なので、加入中の保険があっても更新時に見直して、納得できる商品に加入し直すというのもひとつの方法です。
あわせて読みたい記事
ペット保険の記事一覧
ペット保険を学ぶ
犬の病気を分類から探す
猫の病気を分類から探す
この記事の関連コンテンツ
- ペット保険に関するトラブルとは?
- ペット保険のトラブルケース
- ペット保険でトラブルにならないために
- まとめ
