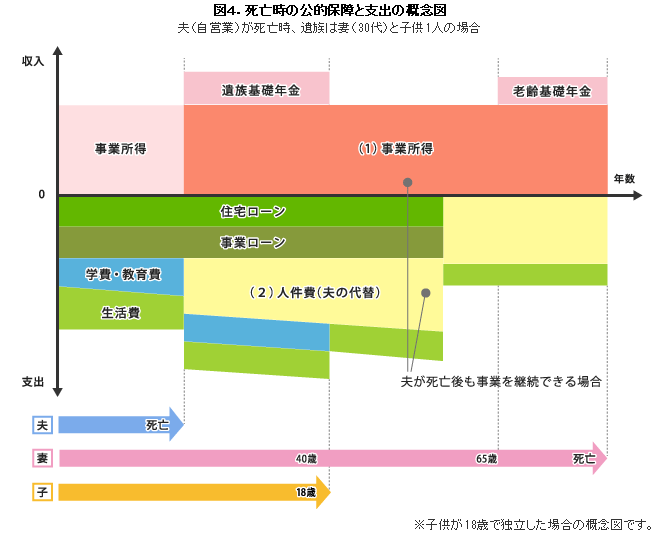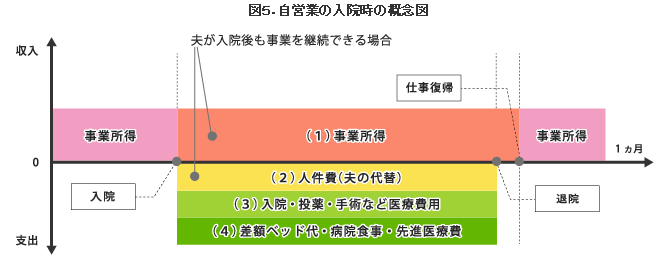- 保険を学ぶ
更新日:2022年7月8日
自営業の保険選び
自営業の方は、会社員や公務員と比較すると
公的保障が薄いため保険の必要性が高くなります。

働き方によって異なる社会保険制度
会社員(正社員、契約社員、派遣社員)、公務員、自営業(請負、SOHO)、パートやアルバイト(フリーター)など、働き方の多様化が進む一方で、社会保険に関しても大きな格差が生じています。独立、起業などで自営業となられた方は、まずどのような社会保障制度の差があるのか把握し、不足分は民間の保険を検討しましょう。
死亡時の社会保障制度
自営業の方は、会社員ほど社会保障に恵まれていません。死亡時の公的保障は「遺族基礎年金」「老齢基礎年金」のみとなります(参照:遺族年金の受給額)。ただし、自営業の場合、夫が亡くなったあとも、経営を継続し所得を得ることが可能なケースもあるため、その場合は、図4に示すような概念図となります。会社・店舗の経営が困難な場合は、夫が亡くなった時点で(1)および(2)が消えた概念図となり、大きく収入が不足します。この不足分を補うように生命保険に加入するようにしましょう。
病気・ケガの社会保障制度
自営業の方も会社員の場合もかかる医療費は同じ費用ですが、会社員と異なり傷病手当も有給休暇もありません。ですので、お店の経営をしている場合は、お店を休業するか、代わりの従業員を雇う必要がでてきます(あらかじめ入院がわかっていないと急に雇うことは難しい)。ですので、収入を補う形で会社員よりも高額な医療保険に加入したり、就業不能保険というものに加入したりしておくといいでしょう。
自営業の方が入院した場合のイメージは、図5のようになります。なお、休業する場合は、(1)および(2)が消えた図となります。(3)については高額療養費制度があるため、1か月の医療費を8万〜15万円程度に抑えることができますが、収入の減少と(4)の費用負担は、避けることができません。
また、自営業者の配偶者が事業の手伝いをしている場合、配偶者が入院してしまうと事業継続に支障が出る可能性があります。その場合は、代わりの従業員を雇う必要があるかもしれません。そのため、配偶者も医療保険に加入しておくと安心です。
店舗・会社の火災保険
事業経営している場合は、自宅を店舗としていたり、別途テナントを借りている場合があるかと思います。火災事故が発生すると事業の継続が困難となるため、十分な火災保険に加入しておく必要があります。
しかし、ほかで加入している保険と個人賠償責任補償が重複していたり、洪水の危険性が低い地域なのに水災補償がセットされていたりするなど、ご加入の保険を見直すことで必要のない補償を省き、保険料を抑えられる場合があるため、複数社の火災保険の見積もりを行って現在の保険料と見比べてみましょう。
また、火災保険は長期契約の一括払いにすると保険料が割安になるため、見直して新しい保険に加入する際は長期契約を検討してみてもいいでしょう。
保険を学ぶ
- 保険の選び方
-
働き方によって異なる社会保険制度
-
死亡時の社会保障制度
-
病気・ケガの社会保障制度
-
店舗・会社の火災保険