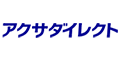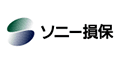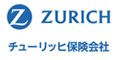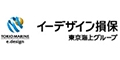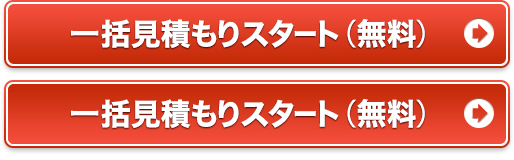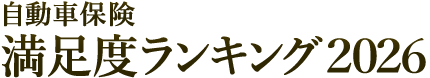先月のご利用数
年齢条件の設定で保険料は安くなる
更新日:2022年5月20日
自動車保険では、契約自動車を運転した際に保険が適用となる人の年齢を制限しておくことで保険料を抑えられます。この年齢条件の設定の仕方で保険料に大きな差が出るケースも。
一方で、年齢条件から外れた人が運転すると事故の際に保険が適用されず補償が受けられない場合もあります。現在の年齢条件と運転する人の年齢をもう一度見直してみましょう。
 疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
年齢条件はどんなふうに決まっている?
生命保険と同じように自動車保険も年齢条件によって保険料が変わってきます。
ただし、生命保険は若い人ほど安く加入できるのに対し、自動車保険では若い人ほど保険料が高くなります。これは過去の事故率のデータの、若年層ほどリスクが高いという統計結果に基づいているためです。
50歳以上60歳未満の年齢はゴールド免許保持者などの優良ドライバーが多い傾向にあり、事故のリスクも低いとの結果が出ており保険料も安くなります。
このような理由から、年齢条件ごとに保険料に差が生じてくるのです。
|
高 い 安 い |
全年齢補償 | 運転者18歳以上を補償 |
|---|---|---|
| 21歳以上補償 | 運転者21歳以上を補償 | |
| 26歳以上補償 | 運転者26歳以上を補償 | |
| 35歳以上補償 | 運転者35歳以上を補償(30歳以上補償の会社もあり) |
若い家族が免許を取ったらすぐ見直しを!
年齢条件とは自動車保険を年齢で制限することを表しています。
例えば、「26歳以上」で、26歳未満の方が運転していて事故を起こしても自動車保険で補償されません。このため、1台の車を家族で共有するケースはくれぐれもご注意を。
年齢条件から外れる人が、「ちょっとだけ」と安易な気持ちで運転して事故を起こしたら大変です。

また、同居の子供が免許を取った時も要注意。「家の車は保険に入っているから大丈夫」と年齢条件のある車を運転して、事故を起こす事例もあるからです。
自動車保険の年齢条件はいつでも変更が可能です。家族が免許をとった場合にはすぐに保険会社に連絡しましょう。
特約を使って保険料を抑えよう!
若いご家族が免許を取り、いままでの年齢条件を変更すると保険料が大幅アップし、驚かれる方も多いようです。そんな場合は運転者の範囲を限定する以下の特約を活用してみてはいかがでしょう?
「家族限定特約」
運転できる人を「(1)契約者本人(記名被保険者)、(2)配偶者、(3)契約者(記名被保険者)または配偶者の同居の親族、(4)契約者(記名被保険者)または配偶者の別居の未婚の子」に限定します。これにより全年齢担保の場合でも、保険料を抑えることができます。
「本人・配偶者限定」
運転できる人を「(1)契約者本人(記名被保険者)、(2)配偶者」に限定します。若い方が免許を取得した場合、ほかの家族や友人などに運転させず自分だけが運転する…という条件なら、かなり保険料を抑えることができます。
年齢条件からはずれる別居の子供や友人が補償されることも
年齢条件を設定しているのに若い人が運転できるケースをご紹介します。
「一般的な保険会社の年齢条件の例」
例えば26歳以上補償にした場合、この年齢条件は次の(1)〜(4)に適用されます。
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者または配偶者の同居親族
(4)上記の人の業務(家事以外)に従事中の使用人
(1)〜(4)以外の人、例えば「帰省中の子供」「別居の親族」「友人・知人」は26歳未満でも補償されることになります。ただし、運転者を限定(家族、本人・配偶者)している場合は補償範囲内での適用となります。ご自身の契約内容が不明な場合、保険会社に問い合わせし正確に把握しておきましょう。
まとめ
- 自動車保険では事故のリスクが高い年齢条件では保険料が高くなります。
- 年齢条件の変更があった場合はすぐ保険会社に連絡しましょう。
- 運転者の範囲を限定する特約によって運転者を絞ることで保険料を抑えることができます。
記事の監修者
-
 平野 雅章 家計相談実績4000件超の相談専門ファイナンシャルプランナー。横浜FP事務所 代表。全国FP相談協会 代表理事。神奈川県立産業技術短大 非常勤講師。CFP(R)。「生活費ポートフォリオ分析(R)」考案者
平野 雅章 家計相談実績4000件超の相談専門ファイナンシャルプランナー。横浜FP事務所 代表。全国FP相談協会 代表理事。神奈川県立産業技術短大 非常勤講師。CFP(R)。「生活費ポートフォリオ分析(R)」考案者 -
 西村 有樹 オフィスクイック代表・フリーランスライター・編集者。
西村 有樹 オフィスクイック代表・フリーランスライター・編集者。
主な執筆分野は企業、金融、保険、マネー系全般。All About自動車保険ガイドなどを手がける。
-

保険料は車の種類や保険金額などの様々な条件によって異なります。保険料が算出されるポイントや相場などについてわかりやすく解説します。
-

自動車保険には走行距離に応じて保険料が安くなるものがあります。どのような仕組みで、どのような人にメリットがあるのでしょうか?
-

自動車保険は掛け捨てなので、できることなら保険料を抑えて加入したいもの。家計も大助かりの割安な自動車保険に加入するコツをご紹介します。
- ※ アクサ損害保険、SBI損保、ソニー損保、SOMPOダイレクト、チューリッヒ保険会社、東京海上ダイレクト、三井ダイレクト損保、楽天損保につきましては、お客様と保険会社との直接の契約になります。
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。
- ※ 掲載している商品やサービス等の情報は、各事業者から提供を受けた情報または各事業者のウェブサイト等にて公開されている特定時点の情報をもとに作成したものです。
- ※ 各種割引や特典は各事業者より提供されます。お申し込みの際は各事業者による注意事項や規約等をよくご確認の上お手続きください。
- ※ 各商品の詳細については、必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等をご確認ください。
- ※ お電話による個別見積もり及びオンラインでの個別見積もりは、各保険会社が運営するサービスであり、当該サービス・見積もりの内容についてご不明な点がございましたら、各保険会社までお問い合わせください。株式会社カカクコムでは応じかねますので、ご了承ください。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止