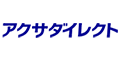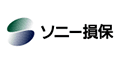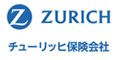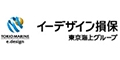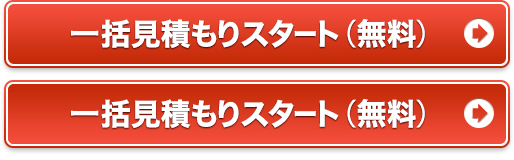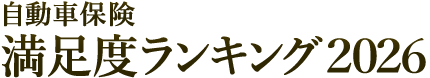先月のご利用数
車両全損時諸費用特約とは?
更新日:2022年5月20日
車両全損時諸費用特約とは、車両が万一全損となった場合、廃車にするために必要な費用、または車の買い替えに必要な諸費用を受け取ることができます。
特約で支払われるのは、車両保険金額の10%(20万円限度)です。車両全損時諸費用特約は車両保険に加入している契約に対し、自動付帯となる保険会社が一般的です。
 疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
疑問が解消したら、あなたに合った保険会社を探しましょう
廃車手続き費用、買い替えの諸費用をカバーできる!
車両全損時諸費用特約とは、事故で車が全損になってしまった場合、廃車にかかる手続き費用、買い替えの諸費用を保険金でカバーできる特約です。
保険金の上限は「車両保険の10%(20万円限度)」としている保険会社がほとんどとなります。
実際に全損とは、どのような状態を指すのでしょうか?
「全損」とは?
- 車が修理不可能な状態
- 修理費が車両保険の保険金額以上になった
- 車両が盗難に遭い発見できない
- ※詳細は各保険会社にお問い合わせください。
このような状況に陥った際、実際にかかったお金ではなく、「車両保険の10%(20万円限度)」を限度に一律で保険金を受け取ることができます。
契約者は受け取った保険金を廃車、新たな車購入に必要となる諸費用として活用できます。
諸費用の内訳・相場は?どのくらいかかるの?
廃車時や車両購入時に実際にどのような手続きや費用が発生するのか、その内訳・相場をそれぞれ確認してみます。
諸費用の内訳と相場
| 項目・手続き | 費用 | |
|---|---|---|
| 廃車 | レッカー費用 | 5,000円〜10,000円 ※距離による |
| 解体費用 | 5,000円〜10,000円 | |
| 永久抹消登録 | 3,000円〜5,000円 ※業者による | |
| 買い替え | 税金 (取得税、自動車税、重量税) |
車種・地域・業者等による |
| 登録費用 | ||
| 車庫証明の代行費用 | ||
| 費用トータル | 中古車の場合:10万円前後 | |
| 新車の場合:車両価格の15-20%程度 200万円の新車:30万円〜40万円 300万円の新車:40万円〜60万円 |
||
- ※金額は目安です。各種条件により異なります。
費用面だけを見ると、車両全損時諸費用特約で廃車費用はカバーできるものの、新車を買う場合の諸費用を全額まかなうことは難しいでしょう。
ただ、一部だけでもカバーできるのは嬉しいところです。
車両全損時諸費用特約のメリット、デメリット
メリット:十分な補償を受けられる
現在乗っている車が車両保険に加入しており、保険金額が200万円前後であるなら、車両保険の10%上限だとしても十分な補償を受けられるメリットがあります。
デメリット:車価によって保険金が変わる
現在乗っている車の車両保険金額が20万円といった場合、受け取れる保険金は2万円となります。保険料にもよりますが、車価が低い場合は付帯するメリットは薄いといえます。
一部の保険会社では、全損時諸費用保険金を倍額にて支払う「全損時諸費用再取得時倍額特約」があります。この場合、車両保険金額の20%(40万円限度)にて保険金を受け取ることができます。この倍額の特約を活用するのもひとつの手段です。
新車特約(車両新価特約)との重複に注意!
新車特約(車両新価特約)は、車両を新車と見なして保険金を支払う特約です。
この特約を使う際、「再取得時諸費用保険金(再登録時諸費用保険金)」を使うことができます。車両を新たに購入する際、費用に充てるために使える保険金ですが、これは車両全損時諸費用特約と機能が重複しています。
よって、「再取得時諸費用保険金(再登録時諸費用保険金)」を受け取ると、車両全損時諸費用特約を使うことはできません。二重に保険金を受け取ることはできないので、事前に確認しておきましょう。
車両全損時諸費用特約の注意点
ノンフリート等級については注意が必要です。この特約を使うには車の全損が条件となっています。つまり全損により車両保険から保険金を受け取り、それとセットで使うイメージです。よって、翌年は3等級ダウンし、保険料がアップします。
なお、全損が条件というものの、車両保険の条件と同じく地震に由来する津波、噴火、陥没などは補償の対象外となります。車両保険と同じ扱いとなるため、注意が必要です。
以下の場合には保険金の支払いを受けることができません。
保険金を受け取れないケース
- 地震、噴火、津波によって生じた損害
- 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害
- 詐欺または横領によって生じた損害
- ご契約されているお車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
- 故障による損害
- ※詳細は各保険会社にお問い合わせください。
通常の事故による全損であれば問題なく保険金を受け取れるものの、それ以外は難しいと認識しておきましょう。
まとめ
- 車両全損時諸費用特約とは、事故で車が全損になってしまった場合、廃車にかかる手続き費用、買い替えの諸費用を保険金でカバーできる特約です。
- 新車特約(車両新価特約)と補償内容が重複する場合があり、その場合は二重に保険金を受け取ることはできません。
- 全損が条件ですが、車両保険の条件と同じく地震に由来する津波、噴火、陥没などは補償の対象外となるため、注意が必要です。
記事の監修者
-
 平野 雅章 家計相談実績4000件超の相談専門ファイナンシャルプランナー。横浜FP事務所 代表。全国FP相談協会 代表理事。神奈川県立産業技術短大 非常勤講師。CFP(R)。「生活費ポートフォリオ分析(R)」考案者
平野 雅章 家計相談実績4000件超の相談専門ファイナンシャルプランナー。横浜FP事務所 代表。全国FP相談協会 代表理事。神奈川県立産業技術短大 非常勤講師。CFP(R)。「生活費ポートフォリオ分析(R)」考案者 -
 西村 有樹 オフィスクイック代表・フリーランスライター・編集者。
西村 有樹 オフィスクイック代表・フリーランスライター・編集者。
主な執筆分野は企業、金融、保険、マネー系全般。All About自動車保険ガイドなどを手がける。
-

事故で車が全損または半損になった場合、新車購入費用を補償してくれる新車特約のメリットや注意点などについて詳しく解説します。
-

自分の車の損害分を補償する車両保険。加入することによるメリットや免責金額の設定の仕方、賢い加入方法などついて詳しく解説します。
-

等級は保険料の割増引率を定めるための区分です。等級はどのように決まるのか、保険料はどのように変わるのかについて詳しく解説します。
- ※ アクサ損害保険、SBI損保、ソニー損保、SOMPOダイレクト、チューリッヒ保険会社、東京海上ダイレクト、三井ダイレクト損保、楽天損保につきましては、お客様と保険会社との直接の契約になります。
- ※ 掲載している情報の正確性については万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。
- ※ 掲載している商品やサービス等の情報は、各事業者から提供を受けた情報または各事業者のウェブサイト等にて公開されている特定時点の情報をもとに作成したものです。
- ※ 各種割引や特典は各事業者より提供されます。お申し込みの際は各事業者による注意事項や規約等をよくご確認の上お手続きください。
- ※ 各商品の詳細については、必ず「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等をご確認ください。
- ※ お電話による個別見積もり及びオンラインでの個別見積もりは、各保険会社が運営するサービスであり、当該サービス・見積もりの内容についてご不明な点がございましたら、各保険会社までお問い合わせください。株式会社カカクコムでは応じかねますので、ご了承ください。
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止