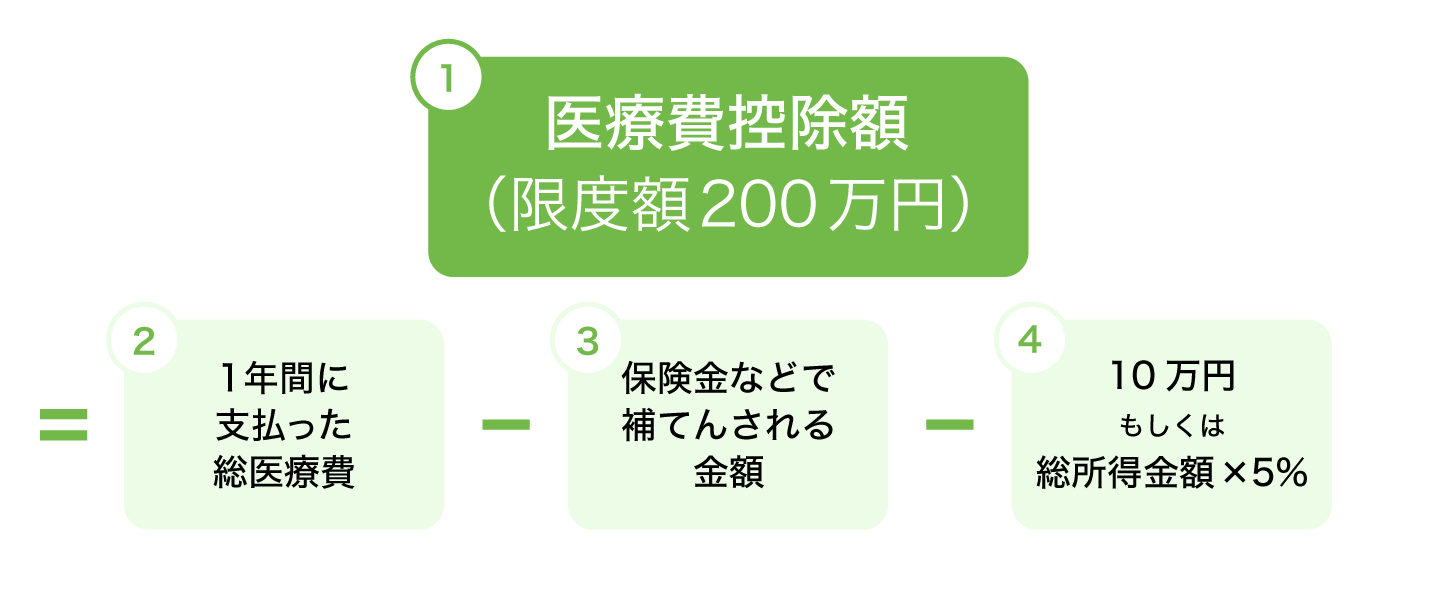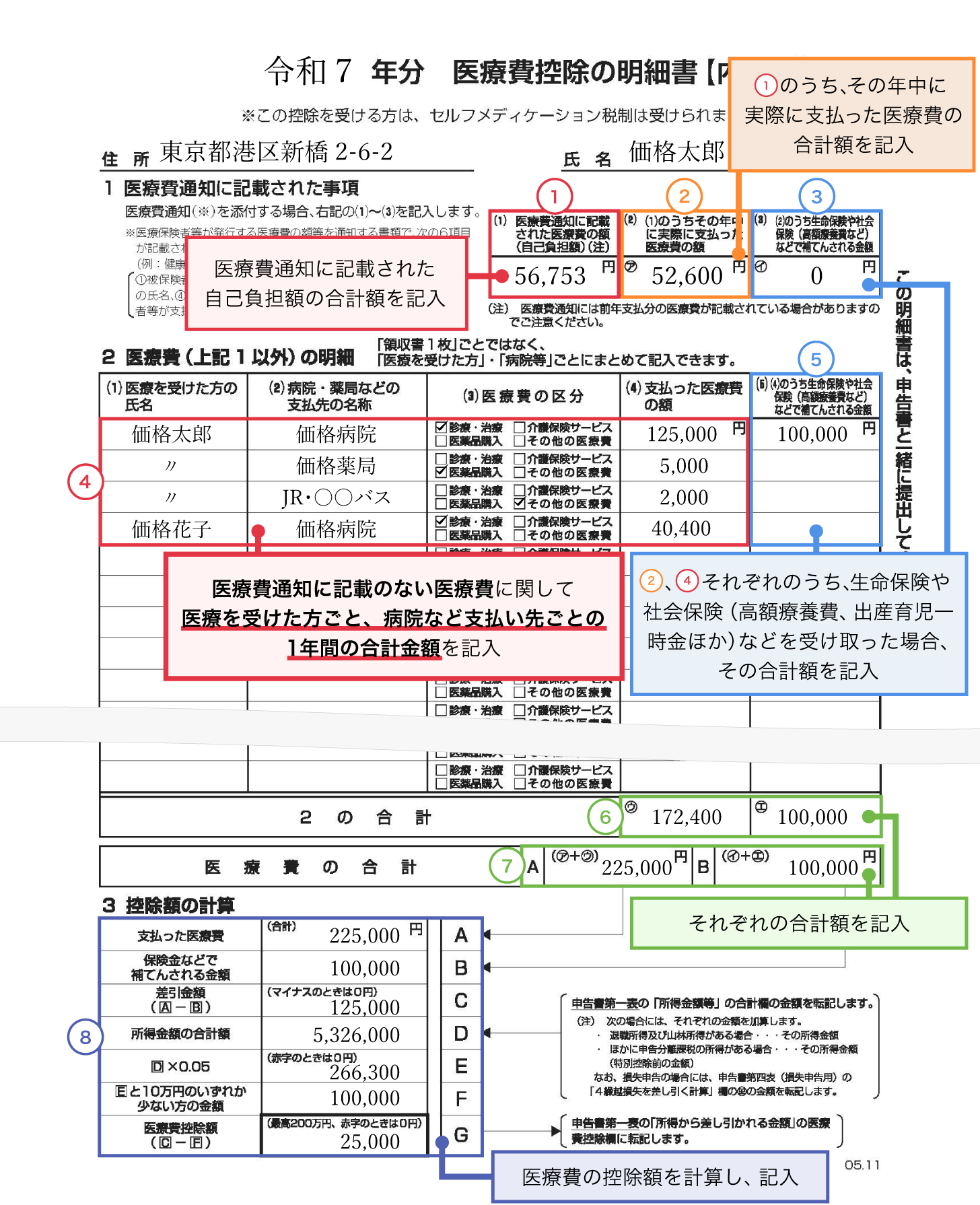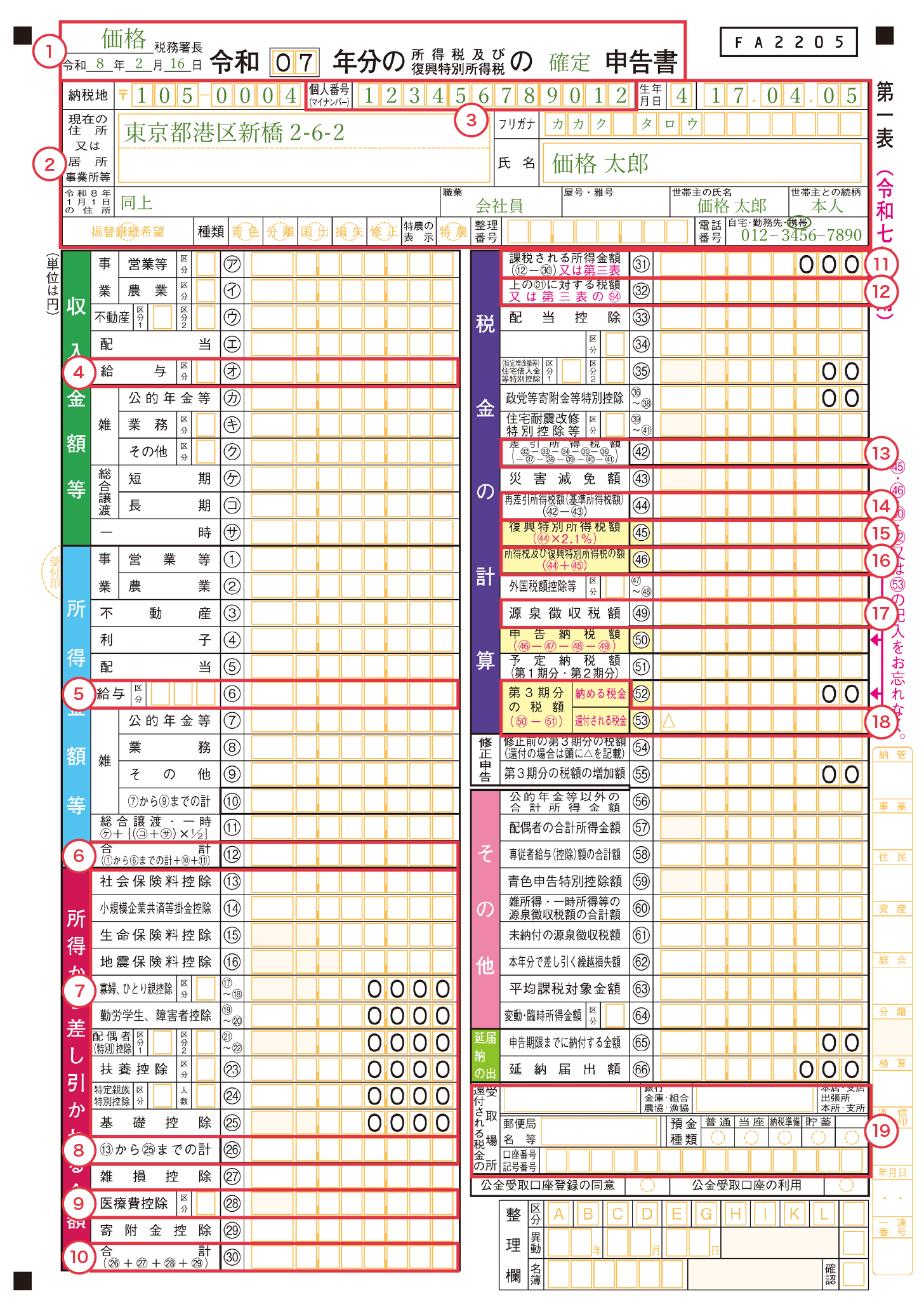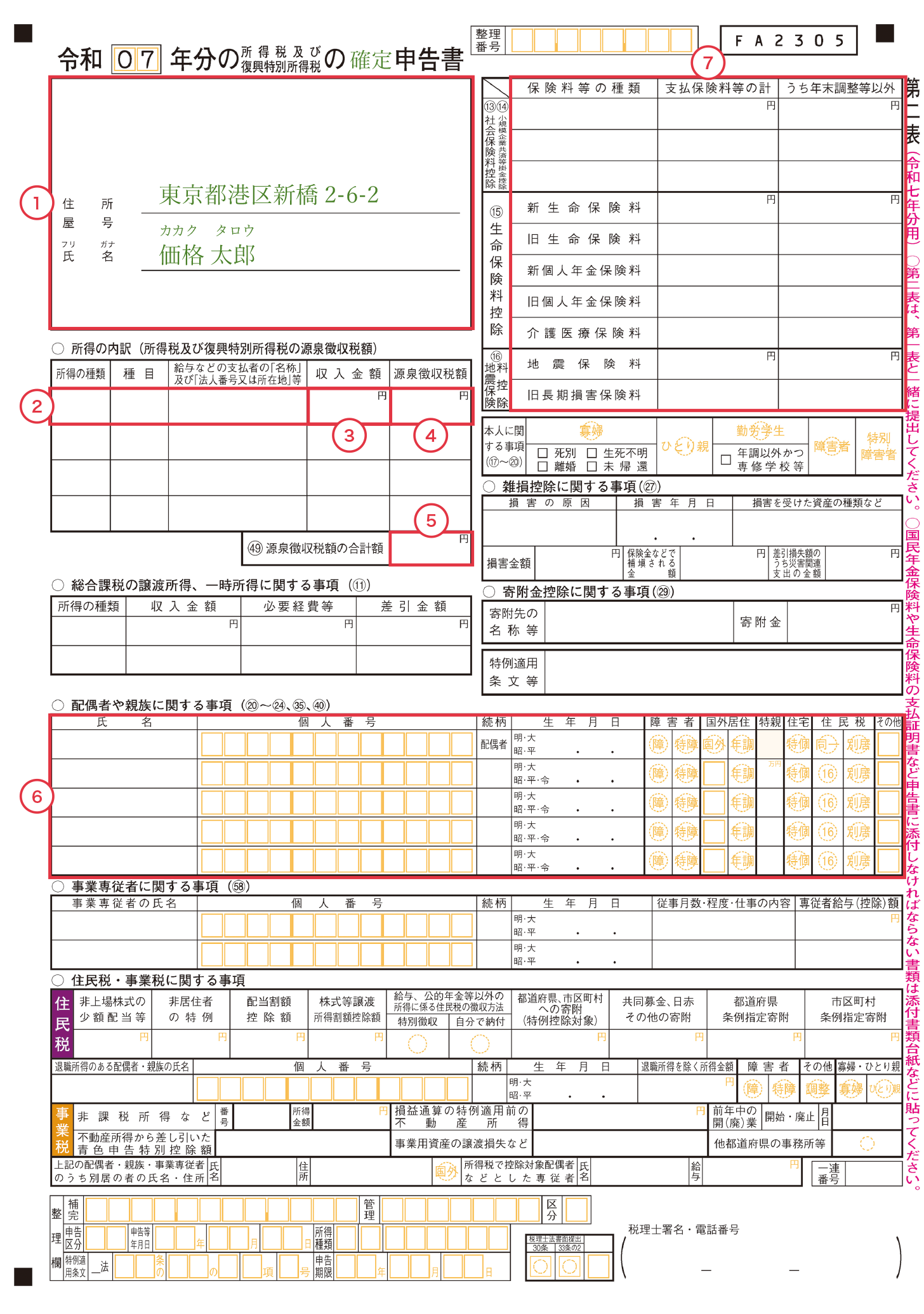�X�V���F2025�N12��16��
�m��\���̈�Ô�T���Ƃ́H�Ώۂ�\���̂����A�����������
�m��\���ň�Ô�T����\�����������m���Ă��܂����H�@�x��������Ô���������ꍇ�A��Ô�T����\������Ə����ł�Z���ł̕��S���y���ł��邱�Ƃ�����܂��B
���̋L���ł́A�T���̑Ώۍ��ڂ�\�����̏������ȂǁA�\���̂�����������܂��B

- ���̋L���̗v�_
-
- ��Ô�T���Ƃ́A�P�N�ԂɎx��������Ô�Ȃǂɉ����ď����T��������Ő��D�����x
- ��Ô�T��������v���́A���̔N��1��1������12��31���Ɏx��������Ô��A�ی����Ȃǂŕ�Ă����z�������������z���A����10���~�ȏ゠��ꍇ�Ȃ�
- ��Ô�T���̑ΏۂƂȂ��Ô�́A��t�Ȃǂɂ��f�Â⎡�Ô�p�̂ق��A���Â�×{�ړI�Ŏx����������
- ���^�����҂ȂǁA�N�������łق��̍T�������ꍇ�͊ҕt�\���A����ȊO�̏ꍇ�͊m��\���ň�Ô�T������
-
���̋L���̊ďC��

-
CFP(R)���i�^1���t�@�C�i���V�����E�v�����j���O�Z�\�m�^�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[�A�R�w�@��w���u�t
���Y ����
1990�N�R�w�@��w���B���Z��[�J�[����O���n�����ی���Ђɓ]�E�B���̌�A�R���T���e�B���O��Аݗ��ɎQ���B 2002�N����t�@�C�i���V�����v�����i�[�Ƃ��Ď�Ɍl�̃��C�t�v�����A�����ی��������A�Z��w���T�|�[�g���̑��k�Ɩ����s���Ă��鑼�A�t�@�C�i���V�����v�����j���O�Ɋւ���u���⎷�M�����s���Ă���B
-
1990�N�R�w�@��w���B���Z��[�J�[����O���n�����ی���Ђɓ]�E�B���̌�A�R���T���e�B���O��Аݗ��ɎQ���B 2002�N����t�@�C�i���V�����v�����i�[�Ƃ��Ď�Ɍl�̃��C�t�v�����A�����ی��������A�Z��w���T�|�[�g���̑��k�Ɩ����s���Ă��鑼�A�t�@�C�i���V�����v�����j���O�Ɋւ���u���⎷�M�����s���Ă���B
�ڎ�
��Ô�T���Ƃ�
��Ô�T���Ƃ́A�P�N�ԂɎx��������Ô�Ȃǂɉ����ď����T��������Ő��D�����x�ł��B
��Ô�T�����ΏۂƂȂ��p�́A���ۂɂ����������Ô�̂ق��A���@��p����@���̐H����A�ʉ@�̂��߂̌�ʔ�ȂǁA���Â�×{��ړI�Ƃ�����Ô�Ȃ��ł��B
�������A��Ô�T������ɂ́A�ȉ��̗v�������Ȃ���Ȃ�܂���B
- ��Ô�T�����邽�߂̗v��
-
- �[�Ŏҁi�T���\���ҁj�܂��́A���v����ɂ���z��ҁA���̂ق��̐e���̂��߂Ɏx��������Ô�Ȃǂł��邱��
- ���̔N�̂P���P������12��31���܂ł̊ԂɎx��������Ô�Ȃǂł��邱��
- ���ۂɎx��������Ô�Ȃǂ���A�����ی��̓��@���t���Ȃǁu��������z�v���������������z���A����10���~�ȏ�ł��邱��
�܂��A��Ô�T������ۂ̎葱�����@�́A�ٗp�`�Ԃ⏊���ɂ���ĈقȂ�܂��B
�Ƃ����̂��A���L�̕\�P�̂悤�ɁA��Ô�T���͔N�������œK�p����Ȃ����߁A�N�������łق��̍T���������^�����҂ł����Ă��A�m��\���̎����ɁA���g�Ŏ葱��������K�v�����邽�߂ł��B
�\�P �\�����K�v�ȏ����T���ƔN�������œK�p�\�ȏ����T��
| �\�����K�v�ȏ����T�� | �N�������œK�p�\�ȏ����T�� | |
|---|---|---|
| �T���̎�� |
|
|
��̓I�ɁA���^�����҂Ȃǂ̏ꍇ�́A�N��������������Ɋҕt�\���i�����������ŋ���Ԃ��Ă��炤�j�ň�Ô�T�����܂��B
����A�l���Ǝ�Ȃǂ́A�m��\���ň�Ô�T�����܂��B
�Ȃ��A�ҕt�\���̐\�����Ԃ͂T�N�Ԃł��B���Ƃ��A2025�N���i�ߘa�V�N���j�̈�Ô�T���̏ꍇ�́A2026�N�i�ߘa�W�N�j�P���P���i�j�`2030�N12��31���i�j���\�����ԂƂȂ�܂��B
�\�����ԓ��ł���A�葱����Y��Ă����N�����A�����̂ڂ��Đ\�����邱�Ƃ��\�ł��B
����ŁA �m��\���ōT������ꍇ�́A2026�N2��16���i���j�`���N3��16���i���j�Ɏ葱�������Ȃ���Ȃ�܂���B
�ҕt�\���A�m��\��������̏ꍇ���A���łɎ��T���̐\�����e�Ɍ��Ȃǂ̕ύX���������ۂ́A�X���̐����ɂďC���葱�����s���܂��B���̊��Ԃ́A�ҕt�\���Ɠ��l�ł��B
��Ô�T���̑Ώۂ̔�p�A�ΏۊO�̔�p
��Ô�T���́A�x���������ׂĂ̈�Ô�ΏۂɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�����A���ÖړI�̈�Ís�ׂɑ��Ďx��������p���Ώۂ̂��߁A���Ƃ��A�C���t���G���U���N�`���̗\�h�ڎ�ȂǁA�a�C�̗\�h���ړI�̂��̂́A�ΏۊO�ƂȂ�܂��B
���̂ق��A���e�ړI�̔�p���ΏۊO�ł��B
�ȉ��̕\�Q�ł́A��Ô�T���̑ΏۂɂȂ��Ô�A�ΏۂɂȂ�Ȃ���Ô�̈����Љ�Ă��܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B
�\�Q ��Ô�T���̑ΏۂɂȂ��Ô�A�ΏۂɂȂ�Ȃ���Ô�̈��
| ���� | �Ώۂ̈�Ô� | �ΏۊO�̈�Ô� |
|---|---|---|
| ���@ �ʉ@ |
|
|
| ��ʔ� |
|
�E���Ɨp�ԂŒʉ@�����ꍇ�̃K�\������A���ԏ�� |
| ���i | �E���Â�×{�ɕK�v�Ȉ��i�̍w����p |
|
| ���� |
|
|
| �o�Y |
|
|
| ���̂ق� |
|
�E���ÖړI�ł͂Ȃ����N�f�f��p |
�Ȃ��A���ی����x�ł́A�v���҂�v�x���҂��A�Ō�t��ی��t�ȊO�ɍݑ�×{�̐��b���˗������ꍇ�A���̔�p����Ô�T���̑ΏۂɂȂ�܂��B
��Ô�T���̑ΏۂƂȂ��Ô�̏ڍׂ́A�ȉ��̃y�[�W�����m�F���������B
��Ô�T���̑ΏۂƂȂ��Ô�i���Œ��j
��Ô�T���̑ΏۂƂȂ���ی����x���ł̋���T�[�r�X���̑Ή��i���Œ��j
��Ô�T���̓���ł���A�Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��Ƃ́H
��Ô�T���̓���Ƃ��āA�Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��i����̈��i�w���z�̏����T�����x�j����������Ă��܂��B
�Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��Ƃ́A���g��v����ɂ���Ƒ��̂��߂ɁA�s�̂̃X�C�b�`OTC���i���w�������ꍇ�A�w���z�̈ꕔ�ŏ����T�������鐧�x�ł��B
�Ώۏ��i�̔N�ԍw���z��12,000�~�����ꍇ�ɓK�p����A�T�����x�z��88,000�~�ł��B
�������A��Ô�T���ƕ��p�ł��Ȃ����߁A�T������ۂ́A��Ô�T�����Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��A�����ꂩ��I�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�ΏۂƂȂ�X�C�b�`OTC���i�Ƃ́A��t�ɂ�鏈��Ⳃ��Ȃ��Ă���ǂȂǂōw���ł�����i�̂��Ƃł��B
���Ƃ��A�������ݒ���A�@���p������Ȃǂ�����܂����A���ׂẴX�C�b�`OTC���i���Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��̑ΏۂɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�Ώۂ̈��i�Ȃǂ̏ڍׂ́A�ȉ��̃y�[�W�����킹�āA���m�F���������B
�Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��i����̈��i�w���z�̏����T�����x�j�ɂ��āi�����J���ȁj
�܂��A�Ώۈ��i�̕��ɂ́A�ȉ��̐}�R�̂悤�ȃ}�[�N���L�ڂ���Ă���ꍇ�����邽�߁A�ڈ��Ƃ��čw���̍ۂɊm�F���Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B
�Ȃ��A�Z���t���f�B�P�[�V�����Ő��́A2026�N�i�ߘa8�N�j12��31���܂œK�p�����\��ł��B
��Ô�T���Ŋҕt���Ƃ��Ă�����߂��Ă���H
��Ô�T���ɂ�����ҕt���Ƃ��Ė߂��Ă�����z�́A��Ô�T���z�ɁA�ېŏ����ɉ������ŗ����|�����킹�邱�ƂŎZ�o�ł��܂��B
��Ô�T���z�̌v�Z���@
�ҕt���z���v�Z����ɂ�����A�܂��͈�Ô�T���z���v�Z���܂��B��Ô�T���z�́A�ȉ��̐}�S�̌v�Z�ŎZ�o�ł��A�T���z�̏����200���~�ł��B
��̐}�S�̂悤�ɁA��Ô�T���z�i�@�j�́A�P�N�Ԃɕ���������Ô�i�A�j����A�ی����Ȃǂŕ�Ăꂽ���z�i�B�j�ƁA10���~�������͑��������z�̂T���i�C�j�������������Ƃŋ��߂��܂��B
��������́A��̐}�S�ɂ���A�`�C�̍��ڂɂ��āA�ڂ����������܂��B
�A �P�N�ԂɎx����������Ô�
���̔N�̂P���P������12��31���܂łɎx��������Ô�����v���܂��B���g�����łȂ��A���v����ɂ���z��҂�e���Ȃǂ̈�Ô�����Z�\�ł��B
�Ȃ��A���̔N�Ɏ��Â��Ă��Ă��x���������N�ɂȂ�ꍇ�́A���N�̈�Ô�T���̑Ώۂł��B
�B �ی����Ȃǂŕ�Ă����z
���Ԃ̐����ی����玡�ÖړI�Ŏ�����ی����Ȃǂ�A���N�ی��Ȃǂ����������z�×{��A�o�Y�玙�ꎞ���Ȃǂ�����ꍇ�A���������v���܂��B
�ی����Ȃǂ̈��́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B
- ��Ô�獷�������ی����Ȃǂ̈��
-
- ���@���t���A��p���t���Ȃ�
�����ی��_��A���Q�ی��_��̈�Ô�ɑ��鋋�t�� - ���z�×{��A�o�Y�玙�ꎞ���Ȃ�
�Љ�ی�����̈�Ô�ɑ��鋋�t�� - ��Ô�ɑ��鑹�Q�������Ȃ�
���̂Ȃǂɂ����Q�ґ�����̔����� - ��Ô�ɑ��鋋�t���A�������Ȃ�
�ݏ��g�D��Ζ��悩��̋��t���〈����
- ���@���t���A��p���t���Ȃ�
�C 10���~�������͑��������z�̂T��
���̔N�̑��������z��200���~�ȏ�̏ꍇ��10���~�A200���~�����̏ꍇ�͑��������z�ɂT�����|�������z���A����Ô�獷�������܂��B
�ҕt���̌v�Z���@
�ҕt���z�́A�u��Ô�T���z�~�ېŏ����ɉ������ŗ��v�ŋ��߂��܂��B
��Ô�T���z�̌v�Z���@���킩�����Ƃ���ŁA��ɉ����Ċҕt���z���v�Z���Ă����܂��傤�B
�܂��́A�ȉ��̉�Ј�A����̏ꍇ���ɁAA����̈�Ô�T���z���v�Z���܂��B
��Ј�A����̏ꍇ
�N��1,000���~�i�ېŏ���550���~�j
��Ô�T���O�̏����Łi���j�{�Z���Ł�125���~
�������[�ɋL�ڂ��ꂽ�����Ŋz
�\�T A���P�N�ԂɎx����������Ô�
| ��Ô�̑Ώێ� | ��Ô�̓��� | �x��������Ô� | �ی����Ȃǂ� ��Ăꂽ���z |
|---|---|---|---|
| A���� | �@�f�@�{���i��p | �U���~ | - |
| A����̔z��� | �A���@�{���Ô�p | 20���~ | �W���~ �i���@���t���j |
| �B�މ@��̒ʉ@�{���i��p | 10���~ | - | |
| �C���@���̍��z�x�b�h�� | �S���~ | - |
��Ô�T���z�́A�P�N�ԂɎx����������Ô��ی����Ȃǂŕ�Ăꂽ���z�ƁA10���~�������͏������z�̂T���������������z�ł��B
A����͑��������z��200���~�ȏ゠�邽�߁A10���~�����������܂��B
�C���@���̍��z�x�b�h��ɂ��āAA����̏ꍇ�͎��ȓs���̂��߁A��Ô�T���̑ΏۊO�ƂȂ�A���Z�ł��܂���B
����Ĉ�Ô�T���z�́A��Ô�v�i�@ + �A + �B�j����ی����Ȃǂŕ�Ăꂽ���z�i�A�̂W���~�j�A10���~������������18���~�ɂȂ�܂��B
���̈�Ô�T���z18���~�ɁA�ېŏ������z�ɉ������ŗ����|�����킹��ƁAA����̊ҕt���z���킩��܂��B
A����̉ېŏ������z��550���~�̂��߁A�ȉ��̕\�U���珊���ŗ���20���ƂȂ�܂��B����̏Z���ł́A�ېŏ������z�ɊW�Ȃ��ꗥ10���ł��B
�\�U �����ł̑��Z�\
| �ېŏ������z | �ŗ� | �T���z |
|---|---|---|
| 195���~���� | 5% | 0�~ |
| 195���~�ȏ� 330���~���� |
10% | 97,500�~ |
| 330���~�ȏ� 695���~���� |
20% | 427,500�~ |
| 695���~�ȏ� 900���~���� |
23% | 636,000�~ |
| 900���~�ȏ� 1,800���~���� |
33% | 1,536,000�~ |
| 1,800���~�ȏ� 4,000���~���� |
40% | 2,796,000�~ |
| 4,000���~�ȏ� | 45% | 4,796,000�~ |
�ȏ�̂��Ƃ���A��Ô�T���z18���~��20���̏����ŗ���K�p���āA�����ł�3��6,000�~�y������܂��B�Z���ł́A�T���z18���~�Ɉꗥ��10����K�p���āA1��8,000�~�y������A���v��5��4,000�~���ł���邱�ƂɂȂ�܂��B
�Ȃ��A�ݐi�ېŐ��x�ɂ���āA�ېŏ������z�������قǏ����ŗ��͍����Ȃ�܂��B���̂��߁A�ېŏ������z�̑���������Ô�T����\�����邱�ƂŁA��茸�łɂȂ���܂��B
��Ô�T���̐\�����@�Ɨ���
��Ô�T���̑Ώۍ��ڂ�T���z�̌v�Z���@�A�ҕt���z�̖ڈ������Ă��܂������A���ۂɁA�ǂ̂悤�Ȏ葱��������ƈ�Ô�T��������̂ł��傤���B
��������́A��ÍT���̎葱���̗�����A���ԂɌ��Ă����܂��傤�B
��Ô�ʒm����̎����ȂǕK�v�ȏ��ނ���������
�܂��́A��Ô�T�����邽�߂ɕK�v�ȏ��ނ�p�ӂ��܂��B�K�v�ȏ��ނ͑S���łS��ނ���A�u��Ô�T���ɕK�v�ȏ��ށv�̍��ڂŏڂ����������܂��B
�Ȃ��A���^�����҂ȂNJҕt�\���ň�Ô�T������ꍇ�ł��A�m��\���̏��ނ��g�p���܂��B
��Ô�T���̖����A�m��\�������쐬����
�K�v�ȏ��ނ����낦����A��Ô�T���̖����Ɗm��\�������\�A���\���쐬���܂��B
���̂R�̏��ނ̏������́A�u��Ô�T�������Ɗm��\�����̏������v�̍��ڂŁA���ނ̌��{�����Ȃ���ڂ����������܂��B
�\�����ԓ��ɁA�Ŗ����ɒ�o����
�L���������������ނ́A�����A�Z���[�̂���Z�����NJ�����Ŗ����ɁA�\�����ԓ��ɒ�o���܂��B��o���@�́A�ȉ��̂R����I�ׂ܂��B
- ��Ô�T���̒�o���@
-
�P.�Ŗ����ɒ��ڏ��ނ����Q����
�Q.���ނ�X������
�R.�d�q�\���V�X�e���ie-Tax�j�𗘗p����
e-Tax�𗘗p����ꍇ�́A�X�}�[�g�t�H����p�\�R�����g���āA�I�����C���Ŏ葱�����\�ł��B�ڂ�����o���@�́A�u�X�}�[�g�t�H���ł̊m��\���̂����v�ŁA�������܂��B
�Ȃ��A��o�̍ۂɂ̓}�C�i���o�[�J�[�h�̒܂��͎ʂ��̓Y�t�ȂǁA�{�l�m�F���ނ��K�v�ł��B
�ҕt�������
�\���葱��������A��P�J���`�P�J�����Ŋҕt�������܂��B
�ҕt���́A�w�肵���a���������ɐU�荞�܂����@�A�Ŋ��̂䂤�����s�e�X�܁A�������͗X�ǂɏo�����Ď����@�A�Q��ނ̎���������܂��B
�Ȃ��A�l���Ǝ�Ȃǂ��m��\���ɂ���Ĕ[�ł���ꍇ�A��Ô�T�����邱�ƂŐŊz���������A�[�Ŋz���y������܂��B
��Ô�T���ɕK�v�ȏ���
�m��\���ň�Ô�T������Ƃ��ɕK�v�ȏ��ނ́A�ȉ��̂S�ł��B
�E��Ô�ʒm
�E��Ô�T���̖���
�E�m��\����
�E�����[
��Ô�ʒm
��Ô�ʒm�́A�������Ă��錒�N�ی��g���Ȃǂ���͂��A��Ô�̊z�Ȃǂ��L�ڂ��ꂽ���ނł��B
��Ô�ʒm�ɋL�ڂ���Ă�����e�́A�ȉ��̂U���ڂł��B
- ��Ô�ʒm�ɋL�ڂ���Ă�����e
-
�P.��ی��҂Ȃǂ̎���
�Q.�×{�����N��
�R.�×{�������̎���
�S.�×{�����a�@�A�f�Ï��A��ǂȂǂ̖���
�T.��ی��҂��x��������Ô�̊z
�U.���N�ی��g���ȂǕی��҂̖���
�����̋L�ړ��e�ɕs�����Ȃ��ꍇ�́A��Ô�ʒm���m��\�����ɓY�t���Ē�o���邱�ƂŁA�u��Ô�T���̖����v�̋L�����ȗ����ł��܂��B�����āA��Ô�̗̎����Ȃǂ̕ۑ����K�v����܂���B
����ŁA�L�ړ��e�ɕs��������ꍇ�́A��Ô�T���̖����ɕs��������⊮���ċL�����܂��B
�Ȃ��A���N�ی��g���ɂ���ẮA�d�q�����⏐���̓d�q�ؖ�����������Ô�ʒm���A�C���^�[�l�b�g��Ŋm�F�A�_�E�����[�h�ł���ꍇ������܂��B
�̎����Ȃǂ͂T�N�ԕۊǂ��Ă����K�v������
��Ô�̎x�������ؖ�����̎����ȂǏ��ނ́A�\�����̒�o�͕s�v�ł����A�؋��Ƃ��Ē����߂���ꍇ�����邽�߁A�\������T�N�Ԃ͕ۊǂ���K�v������܂��B
��̓I�ɂ́A2025�N�i�ߘa�V�N�j���̐\��������ꍇ�́A2026�N�P���P���`2030�N12��31���̂T�N�ԁA�ۊǂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
��Ô�ʒm�ɋL�ڂ̂Ȃ���Ô�̗̎����������ꍇ�A���z���ؖ��ł��鏑�ނ��Ĕ��s���Ă��炦��Ƃ͂�����Ȃ����߁A�������Ȃ��悤�ۊǂ��Ă����܂��傤�B
��Ô�T���̖���
��Ô�T���̖����́A���̔N�Ɏx��������Ô�T���Ώۂ̈�Ô���ʔ�Ȃǂ̔�p���܂Ƃ߂����ނł��B
��Ô�ʒm�̋L�ړ��e�ɕs�����Ȃ��ꍇ�ł��A��Ô�T���̖����ɋL�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ڂ����邽�߁A��Ô�T������ۂ͕K���쐬���܂��B
��Ô�T���̖����́A�Ŗ����Œ��ړ��肷��ق��A�ȉ�����_�E�����[�h�ł��܂��B
��Ô�T���̖����y���z�i���Œ��j
�Ȃ��Ae-Tax�𗘗p����ꍇ�́A���Œ��̃T�C�g�u�m��\�������쐬�R�[�i�[�v�ō쐬�\�ł��B
�m��\����
�m��\�����́A��Ô�T������ۂɁA�����̎�ނɂ�����炸�L���A��o���K�v�ȏ��ނł��B
�Ŗ����Œ��ړ��肷��ق��A�ȉ�����_�E�����[�h�ł��܂��B
�m��\�������\�A���\�i���Œ��j
�Ȃ��Ae-Tax�𗘗p����ꍇ�́A���Œ��̃T�C�g�u�m��\�������쐬�R�[�i�[�v�ō쐬�\�ł��B
�����[
�����[�́A���^���獷�������ꂽ�����ł�Z���łȂǂ̋��z���L�ڂ��ꂽ���ނł��B��ɋ��^�����҂����܂����A���Ƃ��A���҂��狋�^���V�����A�������s���Ă���l���Ǝ�Ȃǂ��A��t�����ꍇ������܂��B
�m��\�����ɂ́A���^��ŋ��̋��z�𐳊m�ɋL�ڂ���K�v�����邽�߁A�����[�̓��e��]�L���邱�ƂɂȂ�܂��B�Ζ���Ȃǂ���������A��ɕۊǂ��Ă����܂��傤�B
��Ô�T���̖����Ɗm��\�����̏�����
��������́A�ҕt�\���ň�Ô�T������ꍇ�́A�u��Ô�T���̖����v�u�m��\�������\�v�u�m��\�������\�v�̏�������������܂��B
��Ô�T���̖����̋L�����@
�ȉ��̐}�V�̋L�����{�����Ȃ���A���ۂɈ�Ô�T���̖����ɋL�����܂��傤�B
�Ȃ��A��Ô�ʒm�̋L�ړ��e�ɕs�����Ȃ��ꍇ�́A��Ô�ʒm��Y�t���Ē�o���\�Ȃ��߁A�ȉ��@�`�B�̍��ڂ̂L�����܂��B
��Ô�T���̖����̋L�����@
- �@�@��Ô�ʒm���̎��ȕ��S�̍��v�z���L��
- ���ߘa�V�N���i2025�N���j�̏ꍇ�A���N1���`12���L�ڕ��̍��v�z���L��
- �A�@�@�̂����A���̔N���Ɏx���������z��̎����ȂǂŊm�F���A���v�z���L��
- �B�@�A�̂����A�����ی��_��A���Q�ی��_��܂��͌��N�ی��@�̋K��ȂǂɊ�Â��Ď�����ی����⋋�t���i���@��t���A���z�×{��A�o�Y�玙�ꎞ���Ȃǁj������ꍇ�A���̋��z���L��
- �C�@��Ô�ʒm�ɋL�ڂ̂Ȃ���Ô�̕K�v�������A�̎����Ɋ�Â��ċL��
- ���̎������Ƃł͂Ȃ��A��Â������A�x���於�̂��ƂɂP�N�����܂Ƃ߂ċL��
- �D�@�C�̂����A�����ی���Љ�ی��ȂǂŎ�������z������ꍇ�A���̋��z���L��
- �E�@��Ô�ʒm�ɋL�ڂ̂Ȃ���Ô�i�C�j�̍��v�A�C�̂��������ی���Љ�ی��ŕ�Ăꂽ�z�i�D�j�̍��v���L��
- �F�@�P�N�ԂɎx��������Ô�̍��v�A��Ô�̂������t���Ȃǂŕ�Ăꂽ���z�̍��v���L��
- �G�@��Ô�̍T���z���v�Z���A�L��
- ���������z�̍��v�z�iD�j�́A�m��\�������\�̏������z���̍��v�z����]�L
- ����Ô�T���z�iG�j�́A�\�������\�̏������獷�����������z�̈�Ô�T�����ɓ]�L
�m��\�������\�A���\�̋L�����@
�����ẮA�ȉ��̐}�W�A�}�X�̋L�����{�����Ȃ���A�m��\�������\�A���\�i���j�ɋL�����Ă����܂��傤�B
�m��\�������\�̋L�����@
- �@�@��o��A��o���Ȃǂ��L��
- �A�@�Z���A�����A���N�����ق��A�K�v�������L��
- �B�@�}�C�i���o�[�i�l�ԍ��j���L��
- �C�@�����[�́u�x�����z�v��]�L
- �D�@�����[�́u���^�����T����̋��z�v��]�L
- �E�@�������z�̍��v�z���L��
- �����^�����ȊO�̏���������ꍇ�́A���������킹�����z���L��
- �F�@�N�������Ŏ葱����Y�ꂽ�T���A�T���z�ɒlj���ύX������ꍇ�́A���̍T���z���L��
- ���lj���ύX�̏ꍇ�́A�N�������Ŏ葱���������z���܂߂��T���z���L��
- ���N������������ύX���Ȃ��ꍇ�́A�L�ڕs�v
- �G�@�����[�́u�����T���̊z�̍��v�z�v��]�L
- �����^�����ȊO�̏���������ꍇ�́A���������킹�����z���L��
- �H�@�u��Ô�T���̖����v���AG���̋��z��]�L
- �I�`�Q�@�e���ɋL�ڂ��ꂽ�v�Z���@�ɉ����ĎZ�o�������z���L��
- �R�@�ҕt���̎��ꏊ�̏��i�a�����������Ȃǁj���L��
�m��\�������\�̋L�����@
- �@�@�Z���A�����Ȃǂ��L��
- �A�@���^�����҂̏ꍇ�́A�����̎�ނɁu���^�v�A��ڂɁu�����v�A�Ζ���̖��̂Ə��ݒn���L��
- �B�@�����[�́u�x�����z�v��]�L
- �C�@�����[�́u�����Ŋz�v��]�L
- �D�@�����Ŋz�̍��v���L��
- ���������P�J���݂̂̏ꍇ�́A�C�̋��z���L��
- �E�@�z��ҁA�}�{�e���̎����A�}�C�i���o�[�i�l�ԍ��j�A�����A���N�����Ȃǂ̕K�v�������L��
- ���N�������Ŋm�肵���z��҂�e���Ɋւ���T���̊z�ɕύX���Ȃ��ꍇ�́A�L�����ȗ��\
- �F�@�N�������Ŏ葱�������Ȃ������ꍇ�A�N�������Ŏ葱�����������e�ɒlj���ύX������ꍇ�́A���̋��z���L��
- ���u�x���ی������̌v�v�ɂ́A�N�������Ŏ葱�����������z�ƁA�lj���ύX�̋��z�����Z���ċL��
- ���u�����N���������ȊO�v�ɂ́A�N�������Ŏ葱�������Ȃ��������ׂĂ̋��z���L��
�X�}�[�g�t�H���ł̊m��\���̂���
��o���ނ̋L��������������A�\�����ԓ��ɕK����o���܂��B
��o���@�́A�Ŗ����ɒ��ڏ��ނ����Q������@�A���ނ�X��������@�A�d�q�\���V�X�e���ie-Tax�j�𗘗p����R�̕��@������܂��B
�����ł́A�X�}�z���g����e-Tax�ł̒�o���@�u�}�C�i���o�[�J�[�h�����v�uID�E�p�X���[�h�����v�ɂ��Đ������܂��B
�}�C�i���o�[�J�[�h����
- �}�C�i�|�[�^���A�g�𗘗p������o�����ł��B
- �@�@�}�C�i���o�[�J�[�h��ǂݎ��
- �A�@�u�m��\�������쐬�R�[�i�[�i���Œ��j�v�Ő\�������쐬
- �B�@�}�C�i�|�[�^���A�g�𗘗p���Ĉ�Ô�ʒm�f�[�^�������擾���A�\�������쐬
- �C�@e-Tax�����o
�ڂ����́A�u�}�C�i�|�[�^���A�g���݃y�[�W�i���Œ��j�v�����m�F���������B
ID�E�p�X���[�h����
- �u�m��\�������쐬�R�[�i�[�v�ł̂ݗ��p�ł����o�����ł��B
- �@�@�Ŗ�����ID�E�p�X���[�h�����̓͏o���쐬�A���M
- ���}�C�i���o�[�J�[�h��IC�J�[�h���[�_���C�^���g���āu�m��\�������쐬�R�[�i�[�v�œ͏o���쐬�A���M���邱�Ƃł��擾�\
- �A�@���s���ꂽID�A�p�X���[�h��e-Tax�Ƀ��O�C��
- �B�@�u�m��\�������쐬�R�[�i�[�v�ň�Ô�T�����ڂ����
- �C�@��Ô�̗̎�����ʒm���̓��e����͂��A�\�������쐬
- �D�@e-Tax�����o
e-Tax�𗘗p���邱�ƂŁA�Ŗ�������Z�@�ւɏo�������ƂȂ��A�X�}�z��p�\�R������ȒP�Ɏ葱�����s���܂��B
�m��\�����s���ۂɖ������Ƃ̂Ȃ��悤�A�X�}�z�Ȃǂł̒�o���@��A�T���̎葱�����@�Ȃǂ����O�Ɋm�F����Ƃ悢�ł��傤�B
���킹�ēǂ݂����L��
-
�y2025�N�i�ߘa�V�N�j�z�N������ �ی����T���\�����̏������ƋL����
�u2025�N(�ߘa�V�N)�� ���^�����҂̕ی����T���\�����v�̏��������A�L����ƂƂ��ɂ킩��₷��������܂��B���̂ق��A�N������������Ƃ��̒��ӓ_�A�m��\���Ƃ̈Ⴂ���������܂��B
-
�����ی����T���Ƃ́H�T���z�̌v�Z���@��T�����x�z�A�Ώۂ̕ی������
�����ی����T���z�ɂ��Čv�Z�̗��V�~�����[�V�����ōT���z��ҕt���z���������ق��A�Ώۂ̕ی��̎�ނ��ڂ���������܂�
���Ȃ��̕ی����͂�����H
��Õی��̓l�b�g�Ŕ�r���������߁I
���i.com�ی��ł͈�Õی��̕ی������ȒP�Ɍ��ς���ł��܂��B
��Õی��̋L���ꗗ
��Õی��Ƃ�
��Õی��̑I�ѕ�
- ��Õی��̑I�ѕ��R�̃|�C���g
- ���@��p���z�̕���
- �������߂̈�Õی�
- ���a������ꍇ�̈�Õی�
- ���@���̍��z�x�b�h��Ƃ́H������]�����ꍇ�Ȃǂ̔�p�⒍�ӓ_�����
- �a�C�ʁE�N��ʂ̕��ϓ��@�����́H�������@���̈�Õ��S�����
- ��Õی��̒ʉ@�ۏ�Ƃ́H�ʉ@�����ł͎��Ȃ��ۏ�̎d�g�݂����
- ��p���t���Ƃ́H���t�Ώۂ̎�p�A�ΏۊO�̎�p�����
- �ی����Ԃƕ�������
- 1���@�Ƃ́H���x�����̐������ƖƐӓ���
- ���@���t���Ƃ́H1��������Őݒ肷��̂��K�H
��Ô�̎x�����x
��Õی��@�֘A���W�E�L��
- ���z�×{��x������A��Õی��͕K�v�Ȃ��I�H
- �l�b�g���ۂ͖{���Ɉ����́H
- ���A����@�Ƃ́H�ʉ@�Ƃ̈Ⴂ���Õی��ŋ��t����������������
- ��Õی��̋��t���������@
- ��Ô�̓_���͕ی��ɊW����́H
- ��Õی��͊|���̂Č^�ƒ��~�^�ǂ����I�ԁH
- �o�Y�ɂ������p�ƕی��̓K�p�͈͂����
- �鉤�؊J�̔�p�͕ی��K�p�ɂȂ�H��Õی��Ŕ�������@
- �������@�ɔ�����ی��͕K�v�H�������@�̉\�����p�����
- ���a�蓖���Ƃ́H�\�����̒�o���@�A�x�������E���z�̌v�Z���@�����
- �q�ǂ��̈�Õی��̕K�v�� ��Ô���ŃJ�o�[�ł���H
- �m��\���̈�Ô�T���Ƃ́H�Ώۂ�\���̂����A�����������
- ��i��Â͂ǂ�������H���z�Ȕ�p�ɔ������i��Õۏ�����
- �K��Ō�͈�Õی��̑ΏہH�K�p�������������
- ����҂͈�Õی��ɉ������ׂ��H�K�v����I�ѕ������
���@��p�̑���
- ��Ô�T���Ƃ�
- ��Ô�T���Ŋҕt���Ƃ��Ă�����߂��Ă���H
- ��Ô�T���̐\�����@�Ɨ���
- ��Ô�T���ɕK�v�ȏ���
- ��Ô�T���̖����Ɗm��\�����̏�����
- �X�}�[�g�t�H���ł̊m��\���̂���