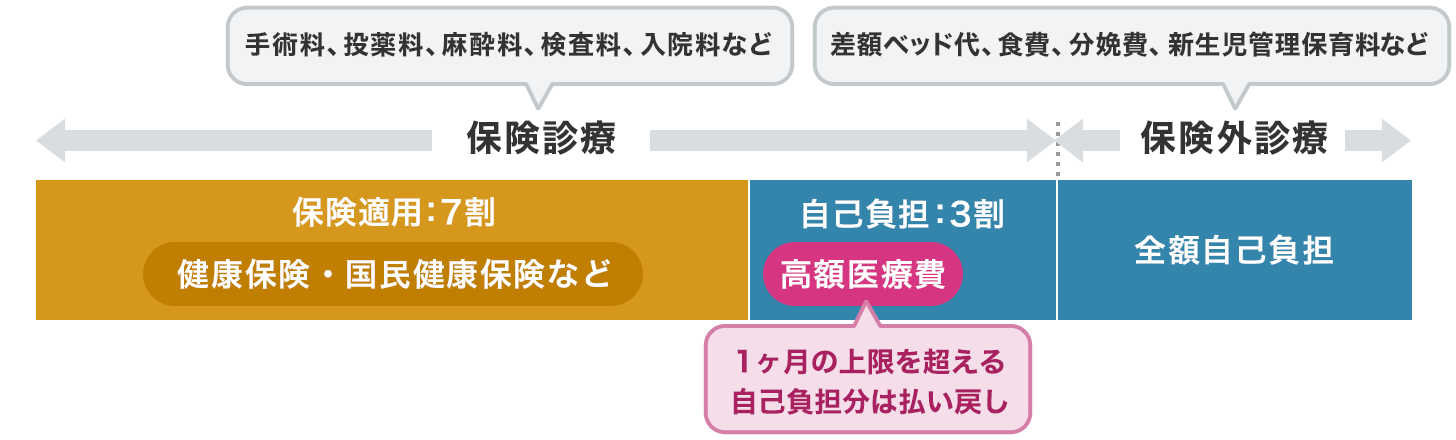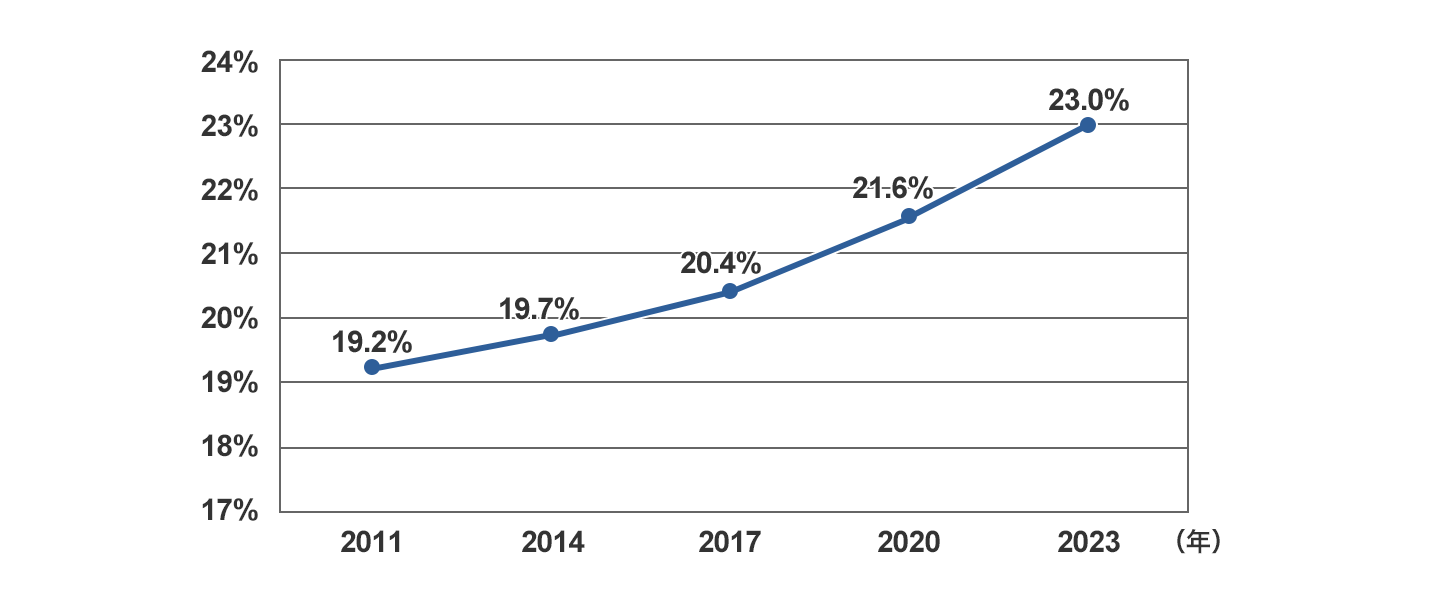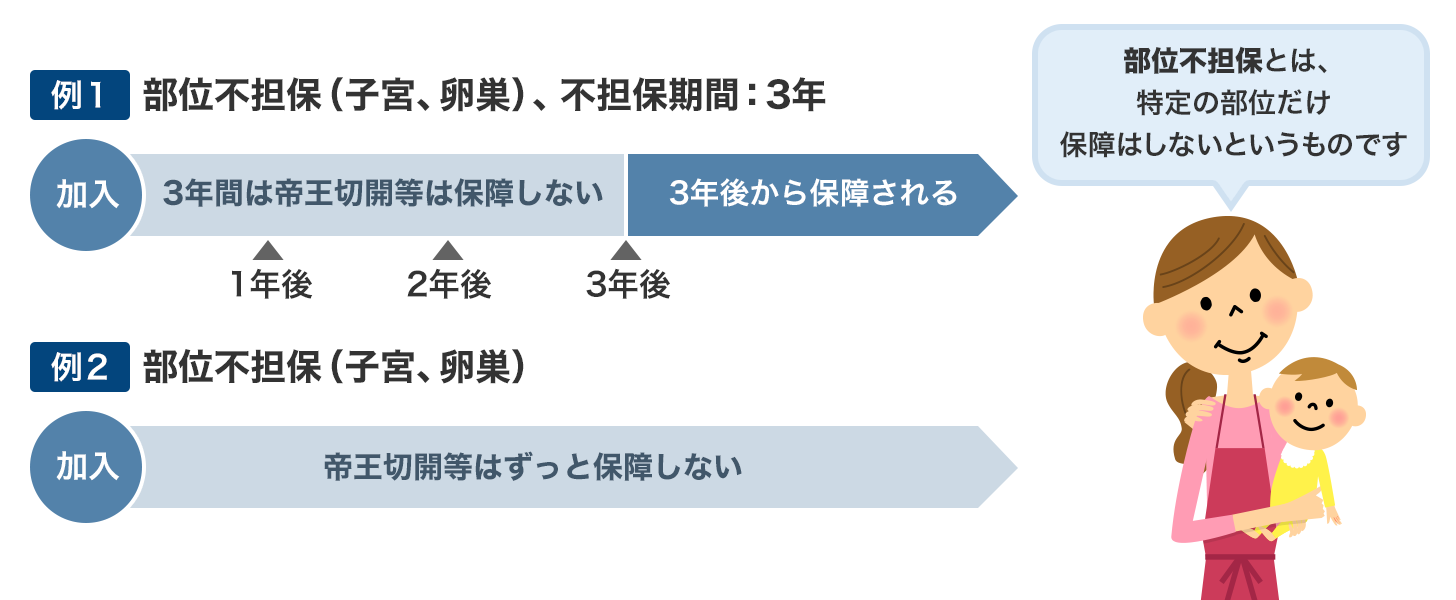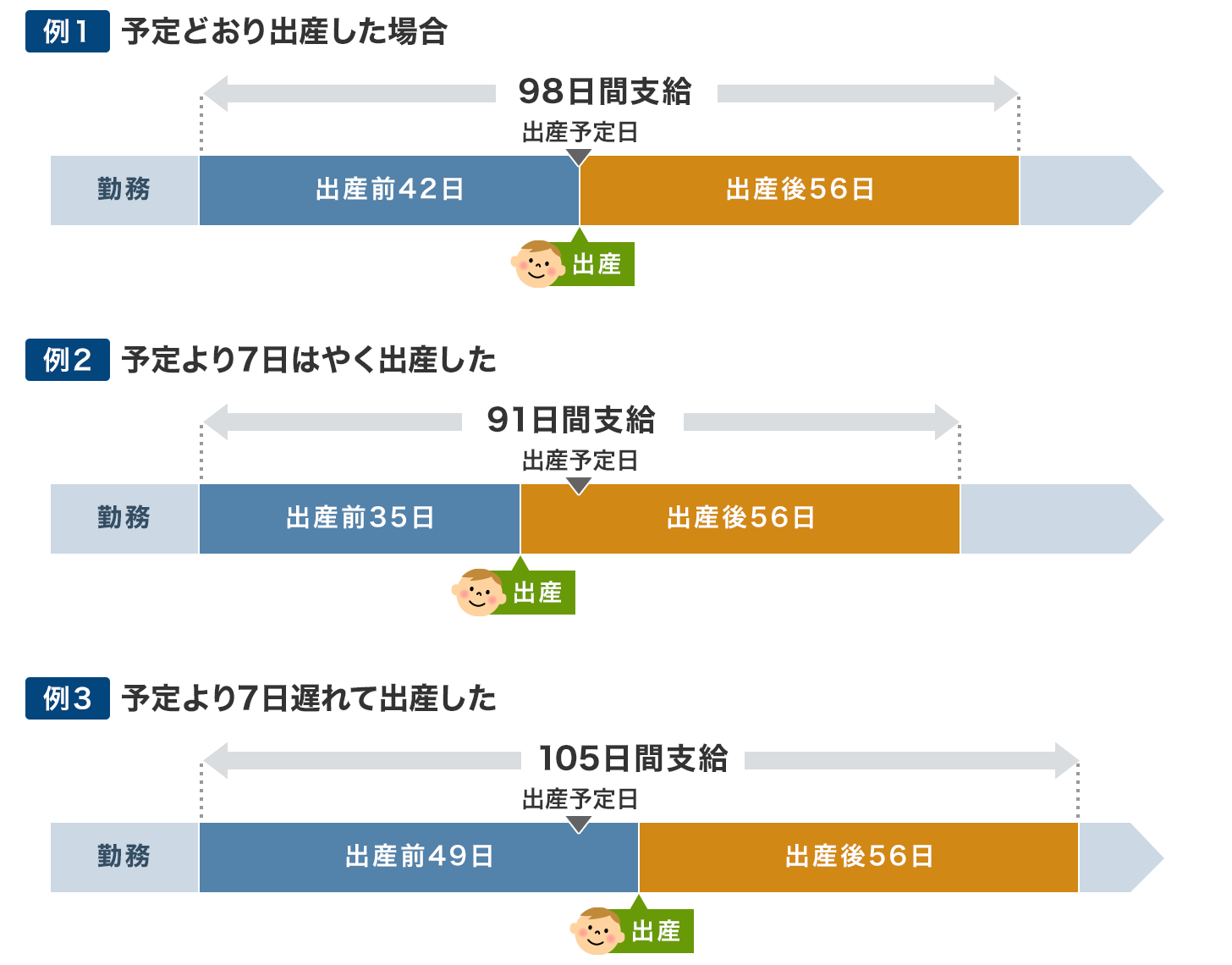�X�V���F2025�N9��10��
�鉤�؊J�̔�p�͕ی��K�p�ɂȂ�H��Õی��Ŕ�������@
�鉤�؊J�ɂ��o�Y�������������Ă��܂��B�鉤�؊J�ł̏o�Y�ɂȂ�Ƃǂ̂��炢�̔�p��������̂ł��傤���H���R���Ƃ͈���Ē鉤�؊J�̈ꕔ�͌��I��Õی��̓K�p�ɂȂ�܂����A�z��O�̏o��S�z�ȕ��́A���Ԃ̈�Õی��ɉ������Ĕ����Ă������ق���������������܂���B

- ���̋L���̗v�_
-
- ���R���͌��I��Ð��x�▯�Ԉ�Õی��̑ΏۊO�����A�鉤�؊J�̔�p�̈ꕔ�͂�������ΏۂɂȂ�
- �鉤�؊J�ł͎��R���؈ȏ�̑z��O�̏o�������\��������
- �z��O�̏o��ɂ͈�Õی��̉������L�������A�������߂̉����^�C�~���O�͔D�P�O
-
���̋L���̊ďC��

-
CFP(R)���i�^1���t�@�C�i���V�����E�v�����j���O�Z�\�m�^�Z��[���A�h�o�C�U�[�^FP�I�t�B�X ���[�N�E���[�N�X��\
���� �G
���s����w�o�ϊw�����ƌ�A ���o�ʼn�ЂɋΖ��B �ݐE���ɏ㋉FP���i�ł���CFP(R)���i���擾�B2003�N�Ƀt�@�C�i���V�����E�v�����i�[�Ƃ��ēƗ����A FP�I�t�B�X ���[�N�E���[�N�X ��ݗ��B�u���q�l�́w�����̐S�z�x����������I�v�����b�g�[�ɁA�l���k�A�Z�~�i�[�u�t�A�G����ށA���M�E��e�Ȃǂ��s���Ă��܂��B �l���k������1,500�����B
-
���s����w�o�ϊw�����ƌ�A ���o�ʼn�ЂɋΖ��B �ݐE���ɏ㋉FP���i�ł���CFP(R)���i���擾�B2003�N�Ƀt�@�C�i���V�����E�v�����i�[�Ƃ��ēƗ����A FP�I�t�B�X ���[�N�E���[�N�X ��ݗ��B�u���q�l�́w�����̐S�z�x����������I�v�����b�g�[�ɁA�l���k�A�Z�~�i�[�u�t�A�G����ށA���M�E��e�Ȃǂ��s���Ă��܂��B �l���k������1,500�����B
�ڎ�
�鉤�؊J�́A���I��Ð��x�̕ی��f�Â▯�Ԃ̈�Õی��̑ΏۂɂȂ�
���R���͐���̕��ł���a�C�ł͂Ȃ����߁A���I��Õی��̓K�p�ɂȂ�܂���B���̂��߁A����������p�̑S�z�����ȕ��S�ɂȂ�܂��B���Ԃ̈�Õی������R���͕ۏ�̑ΏۊO�ł��B
���������āA���@���t�����p���t���Ȃǂ���邱�Ƃ͂ł��܂���B
���R���ł̏o�Y��p
���R���ł̏o�Y��p�́A40���~����65���~���x���Ƃ����Ă��܂����A�o�Y��p�̕��ς́A���̂Ƃ���ł��B
���핪�̕��ϓI�ȏo�Y��p�ɂ��āi2023�N�x�j
| ���� | ���ϒl |
|---|---|
| ���@���� | 5.4�� |
| ���@�� | 122,898�~ |
| �������z | 18,429�~ |
| ���ؗ� | 298,898�~ |
| �V�����Ǘ��ۈ痿 | 51,572�~ |
| �����E��ܗ� | 15,738�~ |
| ���u�E�蓖�� | 17,433�~ |
| �Y�Ȉ�Õ⏞���x | 11,767�~ |
| ���̂ق� | 37,847�~ |
| �D�w���v���S�z | 574,583�~ |
- �a�@�A�f�Ï��A���Y���̍��v
- �D�P�E�o�Y�E�Y��ɂ�����D�Y�w���̎x�������Ɋւ��錟����̎����i�����J���ȁj�����H���č쐬
��L�ɂ��A�D�w�̍��v���S�z�̕��ς͖�57���~�ł��B�����A���̊z�����ׂď�������K�v�͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ�A�q�ǂ������܂ꂽ�Ƃ������N�ی����������N�ی��ɐ\��������ƁA�q�ǂ�1�l�ɂ�50���~�́u�o�Y�玙�ꎞ���v����邱�Ƃ��ł��邩��ł��i�Y�Ȉ�Õ⏞���x�ɉ������Ă��Ȃ���Ë@�ւȂǂŏo�Y�����ꍇ��48.8���~�j�B
�P���v�Z������ƁA�D�w�̍��v���S�z��57���~�Əo�Y�玙�ꎞ����50���~�̍��z�̖�7���~��ڈ��ɏ��������Ă����A�o�Y�ɂƂ��Ȃ���p���J�o�[�ł������ł��B
���݂́A�o�Y�玙�ꎞ������Ë@�ւȂǂɒ��ڎx�����d�g�݁i���ڎx�����x�E���㗝���x�j�����p�ł��A�����͕s������������Ë@�ւȂǂɎx�����悢���ƂɂȂ��Ă��܂��i�o�Y��p���o�Y�玙�ꎞ���������ꍇ�́A���z�����܂��j�B
�鉤�؊J�̏ꍇ�͎��R��������p��������
�鉤�؊J�Ȃǂُ̈핪�̏ꍇ���u�o�Y�玙�ꎞ���v�����܂����A���R���ł͂�����Ȃ���p��������܂��B
���@�������A���R���̏ꍇ�͕���5.4���ł����A�鉤�؊J�̏ꍇ��6������10�����x�A�Y��̌o�߂ɂ���Ă�10���ȏ�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�������A�鉤�؊J�ɂƂ��Ȃ���p�Ⓤ��A���ˁA�����A�����A���@���Ȃǂ̈�Ô�͌��I��Õی��̓K�p�ɂȂ�A���ȕ��S�z��3���ł��݂܂��B�܂��A���I��Õی����K�p�ɂȂ��p�����z�×{��x���K�p����邽�߁A1�J���̏���z���鎩�ȕ��S�����͕����߂���܂��B
�Ȃ��A���z�x�b�h����H��A���ؗ��A�V�����Ǘ��ۈ痿�Ȃnj��I��Õی����K�p����Ȃ���p�́A�S�z���ȕ��S�ɂȂ�܂��B
�z��O�̏o��ɔ�����ɂ́A���Ԃ���Õی��ɉ������Ă������Ƃ��L���ł��B�Ȃ��Ȃ�A���Ԃ̈�Õی��ł��鉤�؊J�Ȃǂُ̈핪���ۏ�ΏۂɂȂ邩��ł��B
���ׂĂ̖��Ԃ̈�Õی����鉤�؊J��ۏႵ�Ă���Ƃ͂�����܂���̂ŁA��������O�Ɍ_����e���悭�m�F���Ă���������
���l�C�̈�Õی����킩��I
���Ԃ̈�Õی��Œ鉤�؊J�̔�p���J�o�[
�鉤�؊J�ŏo�Y���邱�ƂɂȂ邩�ǂ����́A�D�P�������ƂłȂ���킩��܂���B�܂��A�D�P���ɂ͎��R����\�肵�Ă��Ă��A�o�Y���̏ɂ���Ă͋}�ɒ鉤�؊J�ɂȂ�ꍇ������܂��B
-
- �I��鉤�؊J�p�F20��1400�~
- �ً}�鉤�؊J�p�F22��2000�~
- ���G�ȏꍇ�̓v���X2���~������
- �鉤�؊J�́u��p���v�͂ǂ��̕a�@�ł������ł��i2024�N�x�f�Õ�V�_�����j
- ��L�̎�p�������łȂ��A���܂��܂Ȕ�p��������܂�
4.3�l��1�l���鉤�؊J�ŏo�Y���Ă���
���̃O���t�́A���،����ɑ���鉤�؊J�̊����̐��ڂ������Ă��܂��B
�鉤�؊J�̊����͔N�X�㏸���Ă���A2023�N�͖�23���A4.3�l��1�l���鉤�؊J�ŏo�Y���Ă��܂��B
���̌�����݂�ƁA�D�P�����l�͂���ł��鉤�؊J�ŏo�Y���邩������Ȃ��ƍl���Ă������ق����悳�����ł��B
�鉤�؊J�ł̏o�Y�ɔ����āA���炩���ߖ��Ԃ̈�Õی��ɉ������Ă����A���@���t�����p���t�������A�z��O�̏o����J�o�[�ł��܂��B
��Õی��ɉ������Ă����ꍇ�ŁA�鉤�؊J�ɂȂ����Ƃ��̔�p����
�鉤�؊J�ł̏o�Y��p�i���@������9���j
���I��Õی��K�p���i3�����S�E���z�×{��K�p��j�F8��1230�~
����E���̑��F61��7720�~
�o�Y��p���v�F69��8950�~�c�@
�������Ă�����Õی�����̋��t��
���@���t���F9���~�i1���~�~9���j
��p���t���F10���~
���t�����v�F19���~�c�A
���I��Ð��x���������o�Y�玙�ꎞ���F50���~�c�B
�ŏI�I�Ȏ��ȕ��S�z�F�@69��8950�~�|�i�A19���~�{�B50���~�j��8,590�~
��L�́A�鉤�؊J�ɂ��o�Y�ɖ�70���~�̔�p�������������̂́A��Õی��ɉ������Ă����������œ��@���t���Ǝ�p���t��19���~�����A�ŏI�I�Ȏ��ȕ��S��1���~�����Ɏ��܂����P�[�X�ł��B
���l�C�̈�Õی����킩��I
���Ԃ̈�Õی��ɉ������ׂ��^�C�~���O�́H
���Ԃ̈�Õی��ɉ�������œK�ȃ^�C�~���O�́A�D�P�O�ł��B�Ȃ��Ȃ�A�D�P���̐l�́A�D�P���Ă��Ȃ��l�������X�N�������Ɛ����ی���Ђ����f���邩��ł��B
���̂��߁A�\�����݂̎����ɂ���Ă͉����ł��Ȃ�������A�����ł����Ƃ��Ă��قƂ�ǂ̏ꍇ�A���ʕs�S�ۂƂ������ʏ��������܂��B
���ʏ����Ƃ́A�鉤�؊J�ȂǂɂƂ��Ȃ����@���p�͕ۏ�̑ΏۊO�Ƃ���Ƃ������̂ł��B
�������A����ł���Õی��ɉ������Ă����A�D�P��o�Y�ɊW�̂Ȃ��a�C��P�K�ł̓��@�A��p�͕ۏႳ��܂��B�������A�鉤�؊J�Ȃǂ̃��X�N�ɔ�����ړI�ʼn������悤�Ƃ���l�̕s�����������邱�Ƃ͂ł��܂���B
�Ȃ��A�ŏ��̔D�P���ɓ��ʏ����t���ʼn������A���̏o�Y�����R���������ꍇ�A����̔D�P�ł͓��ʏ������͂���A�鉤�؊J�Ȃǂ��ۏႳ��邱�Ƃ�����܂���
�����̏ꍇ�́A�Ɛg����A���邢�́A������ł��D�P�O�̎����ɖ��Ԃ̈�Õی��ɉ������Ă����̂��悢�ł��傤�B
��������A���ʏ����������ƂȂ��A�o�Y���̒鉤�؊J�Ȃǂ��܂߁A���L���a�C��P�K�ɂ����@�A��p�̕ۏ���m�ۂł��܂��B
���l�C�̈�Õی����킩��I
�ŏ��̏o�Y���鉤�؊J���ƁA���̌�ɉ������Ă��ۏႳ��Ȃ��c
�ŏ��̏o�Y���鉤�؊J���ƁA���̌�A����ɔ����Ĉ�Õی��ɉ������悤�Ƃ��Ă��A�������ʼn�������͍̂���ł��B
��Õی��̐\�����݂�����ۂɂ́A���m���ɁA���̂Ƃ��̌��N��Ԃ�ߋ��̕a���Ȃǂ𐳒��ɋL�ڂ��Ȃ���Ȃ�܂���B
���m���̒��ɂ���u�ߋ�5�N�ȓ��ɒ鉤�؊J���܂ޔD�P�E���ɂƂ��Ȃ��ُ�œ��@���p���������Ƃ�����܂����v�Ƃ�������Ɂu�͂��v�Ɖ���ƁA�قƂ�ǂ̏ꍇ�œ��ʏ��������A����̔D�P�A�o�Y�ł��ۏႳ��܂���B
�鉤�؊J�ȊO�ɂ��A�D�P�E���ɂƂ��Ȃ��ُ�Ƃ��Ď��̂悤�ȏǏY�����܂��B����炪�ߋ�5�N�ȓ��Ȃǂɂ���ƍ��m���K�v�ɂȂ�A���ʏ��������\��������܂��B
- �ی���Ђ⏤�i�ɂ���ĈقȂ�܂��B
- �ؔ����Y
- ��Y�i�z�����E��q���j
- ���Y
- �q�{��ǖ��͏�
- �����j��
- �O�u�ٔ�
- �D�P���ŏǁi�D�P�������nj�Q�j
- �D�P���j�i���j
- �q�{�O�D�P
- �D�P���ŏ�
�Ȃ�
���l�C�̈�Õی����킩��I
�o�Y�ɂƂ��Ȃ��č�����x������邨���́H
�q�ǂ�1�l�ɂ�50���~�����炦��
���R����A�鉤�؊J�Ȃǂُ̈핪�ɂ�����炸�A�o�Y�������Ƃ��ɂ͌��N�ی��⍑�����N�ی��ɐ\������Əo�Y�玙�ꎞ���Ƃ��āA�q�ǂ�1�l�ɂ�50���~�i�Y�Ȉ�Õ⏞���x�ɉ������Ă��Ȃ���Ë@�ւȂǂŏo�Y�����ꍇ��48.8���~�j�����邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ܂����B
�o�Y�玙�ꎞ�������炦��o�Y�Ƃ́A�D�P13�T�i85���j�ȏ�̐��Y�i���Y�j�A���Y�i���Y�j�A�l�H�D�P����̂��Ƃł���
�Y�O�Y��x�ɂ́A�o�Y�蓖�������炦��
��Ј��̐l�ŁA�Y�O�Y��x�ɂ��Ƃ��ĉ�Ђ��狋���̎x�������Ȃ��ꍇ�́A�o�Y�蓖�������܂��B
�x�����Ԃ͌����Ƃ��ďo�Y�\����ȑO42������o�Y���̗����ȍ~56���܂ł͈͓̔��ŁA��Ђ��x�����̎x�������Ȃ��������Ԃł��B���Ȃ݂ɁA�o�Y���\������x�ꂽ�ꍇ�́A���̒x�ꂽ���Ԃ��o�Y�蓖�������炦�܂��B
�x���z�͋��^��2�^3�����z�ł��B�o�Y�蓖���̊z��菭�Ȃ������������Ă���ꍇ�́A���z���x������܂��B
�o�Y��p�͈�Ô�T���̑ΏۂɂȂ邱�Ƃ�
�o�Y�ɂƂ��Ȃ����܂��܂Ȕ�p�̈ꕔ�́A��Ô�T���̑Ώۂɂ��Ȃ�A�m��\��������ΐŋ��̊ҕt����܂��B
���R����A�鉤�؊J�Ȃǂُ̈핪�ɊW�Ȃ��A�D�P��̒�����f�⌟���̔�p�A�ʉ@��p�A���@�E��p�̔�p�A�o�Y�œ��@���邽�߂̃^�N�V�[����܂ތ�ʔ�A���@���ɕa�@�Ɏx�����H����Ȃǂ��ΏۂɂȂ�܂��B
- �֘A�y�[�W�@�m��\�� ��Ô�T���̑Ώۂ�\�����@�Əڂ���������
��Ô�T���z���v�Z����Ƃ��́A��Ô��o�Y�玙�ꎞ���Ȃǂ▯�Ԃ̈�Õی������������t�������������Ȃ��Ƃ����܂���i�o�Y�蓖���͍��������Ȃ���OK�j
���ꂩ��D�P�A�o�Y���}���鏗���ɂƂ��āA�鉤�؊J�ɂ��o�Y�͌����Ē��������Ƃł͂���܂���B���ꂾ���ɁA�\�z�O�̏o��ɔ�����Ȃ�A�Ɛg�̂Ƃ����A������ł��D�P�O�̑��������Ɉ�Õی��̉�������������̂��L���ł��B
�Ⴂ�����ɉ������Ă����A�ی����������ƌv�ւ̕��S���Ⴍ�}�����܂��B
�܂��A�鉤�؊J�ɂ����炸�A���̂ق��̕��L���a�C��P�K�ɂ����@�A��p�ɔ���������������Ă��邽�߁A���S���܂��B
���l�C�̈�Õی����킩��I
���킹�ēǂ݂����L��
���Ȃ��̕ی����͂�����H
��Õی��̓l�b�g�Ŕ�r���������߁I
���i.com�ی��ł͈�Õی��̕ی������ȒP�Ɍ��ς���ł��܂��B
��Õی��̋L���ꗗ
��Õی��Ƃ�
��Õی��̑I�ѕ�
- ��Õی��̑I�ѕ��R�̃|�C���g
- ���@��p���z�̕���
- �������߂̈�Õی�
- ���a������ꍇ�̈�Õی�
- ���@���̍��z�x�b�h��Ƃ́H������]�����ꍇ�Ȃǂ̔�p�⒍�ӓ_�����
- �a�C�ʁE�N��ʂ̕��ϓ��@�����́H�������@���̈�Õ��S�����
- ��Õی��̒ʉ@�ۏ�Ƃ́H�ʉ@�����ł͎��Ȃ��ۏ�̎d�g�݂����
- ��p���t���Ƃ́H���t�Ώۂ̎�p�A�ΏۊO�̎�p�����
- �ی����Ԃƕ�������
- 1���@�Ƃ́H���x�����̐������ƖƐӓ���
- ���@���t���Ƃ́H1��������Őݒ肷��̂��K�H
��Ô�̎x�����x
��Õی��@�֘A���W�E�L��
- ���z�×{��x������A��Õی��͕K�v�Ȃ��I�H
- �l�b�g���ۂ͖{���Ɉ����́H
- ���A����@�Ƃ́H�ʉ@�Ƃ̈Ⴂ���Õی��ŋ��t����������������
- ��Õی��̋��t���������@
- ��Ô�̓_���͕ی��ɊW����́H
- ��Õی��͊|���̂Č^�ƒ��~�^�ǂ����I�ԁH
- �o�Y�ɂ������p�ƕی��̓K�p�͈͂����
- �鉤�؊J�̔�p�͕ی��K�p�ɂȂ�H��Õی��Ŕ�������@
- �������@�ɔ�����ی��͕K�v�H�������@�̉\�����p�����
- ���a�蓖���Ƃ́H�\�����̒�o���@�A�x�������E���z�̌v�Z���@�����
- �q�ǂ��̈�Õی��̕K�v�� ��Ô���ŃJ�o�[�ł���H
- �m��\���̈�Ô�T���Ƃ́H�Ώۂ�\���̂����A�����������
- ��i��Â͂ǂ�������H���z�Ȕ�p�ɔ������i��Õۏ�����
- �K��Ō�͈�Õی��̑ΏہH�K�p�������������
- ����҂͈�Õی��ɉ������ׂ��H�K�v����I�ѕ������
���@��p�̑���
- �鉤�؊J�́A���I��Ð��x�̕ی��f�Â▯�Ԃ̈�Õی��̑ΏۂɂȂ�
- ���Ԃ̈�Õی��Œ鉤�؊J�̔�p���J�o�[
- ���Ԃ̈�Õی��ɉ������ׂ��^�C�~���O�́H
- �ŏ��̏o�Y���鉤�؊J���ƁA���̌�ɉ������Ă��ۏႳ��Ȃ��c
- �o�Y�ɂƂ��Ȃ��č�����x������邨���́H